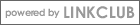06 January
オーストラリアの憂鬱
昨日の夕方の事。仕事場への道を急いでいると、ふいに男が僕の行く手をふさいだ。
「金、くんねぇか?」
呂律の回らない口調、ふらつく足取り、濁った眼。
肌の色は黒褐色、鼻がつぶれ、歯はヤニで汚い。
身にまとった衣服は古びて薄汚れている。
見ると、男の後ろには同じように汚い身なりをした若い男女が車座になって座っている。
同じように肌は黒い。酒を飲んでいるのか、それともある種のドラッグか、陶然となって現実感を失っているようだ。
正直言って、あまりかかわり合いになりたくない連中である。
発している雰囲気がやばい。
僕は一言「No」とだけ呟いて、足早にその場を去った。
彼らは別に文句を言うでもなく、追いかけて来るでもなかった。
この人達がいわゆるアボリジニである。
諸説あるが、このオーストラリア大陸に12万年前から住んでいたとされる。
ヨーロッパ人が彼らの伝統的な生活様式を根本から破壊してしまう18世紀まで、深い孤絶の内に長い長い夢を生きてきた人々だ。
ドリームタイムとはアボリジニ達の神話体系の総称だ。
その文化は呪術的かつスピリチャルな要素が濃く、ユニークな描画や巨大な筒状の楽器ディジリジュなどはつとに有名である。
先住民の受難について簡単に説明しよう。
数万年に渡って永々と独自の生活を続けて来たアボリジニの住む大陸を、ある時船で乗り付けたヨーロッパ人が「発見」した。
まずオランダ人、そしてイギリス人がやって来た。
彼らは先住民を駆逐し、殺害し、女を犯し、土地を簒奪し、沿岸部に住み着いた。
かつて南北アメリカ大陸で行なわれた事が、そっくり同じように繰り返された。
先住民は欧州人が持ち込んだ病原菌でばたばたと倒れた。免疫がなかったからだ。
アルコールも深刻な問題だった。元々飲酒習慣のなかったアボリジニ達の身体は徹底的に破壊された。
スポーツハンティングと称して、アボリジニを狩る事も行なわれた。
19世紀半ばには法律によって「狩猟」が認められた。
子供達を大量に拉致し、施設に入れて無理矢理「進んだ教育」を受けさせた。
民族の血を絶やす為だったとも言われている。
実際、現在では混血化が進み、純粋なアボリジニは極端に少なくなったとされている。
その後時代が下り、この国にも民主主義が根付くや、先住民に対する数々の悪行に対して非難の声が上がり始めた。
国家元首が公式に謝罪し、部分的に土地の返還が行なわれ、都市部のアボリジニに対する保護政策が採られた。
しかし、問題は山積みだ。
働かなくても生きて行けるようになった都市部のアボリジニは、飲みつけない酒を飲んで、そこら辺でへべれけになっているという状態が現出した。
アボリジニの就職を優遇する制度に白人達が「逆差別だ」と声を荒げるという事態も起きた。
歴史に起因する構造的な問題なので、首相が謝ったくらいでは何も解決しないのだ。
現在、先住民の末裔達の一部は、路上で昼日中から酒を飲み、酩酊し、大声で卑猥な冗談を言い、時に通行人に金をたかるという浮浪者同然の生活をしている。
皆が皆そうという訳ではない。中には自立して立派に生きているアボリジニもいる。
だが、街のそこかしこで見かける「ちょっとやばめ」の人々にアボリジニが多いというのは事実である。
当然、彼らは犯罪にもある程度コミットする事になる。
この公園は夜になるとアボリジニのたまり場になるから絶対に近寄っちゃいけないよ、というような「普通の」オーストラリア人のアドバイスを受けた事も数知れない。
ブーメランや、絵画や、ディジリジュが、アボリジニ的なアイコンとして広く認知されているのと同じように、現実の彼らは社会のお荷物であり、厄介者であり、犯罪者予備軍として認知されている。
要するにヒエラルキーの最底辺にいるのが彼らなのである。
ある時、イギリス系オーストラリア人の家へ招かれた。
ホストマザーは60近い歳で、大層酒好きだった。その日は少し飲み過ぎていたのだろう。
初対面の僕に対して問わず語りに「現代オーストラリアの抱える憂鬱」について話し始めた。
「最近はオーストラリアにもアフリカや中東から移民が増えて来たけれど、本当はあんなのに来て欲しくないのよね。
彼らはレイジーだし、治安も悪くなるし。
アジア人はオーケーよ。特にあなた方ジャパニーズはね。
真面目に働くし、有能な人が多いし、この国に貢献してると思う。
でもブラックピープルはダメ」
この人は多分酒が入っていなければ、こんな発言はしなかったはずだ。
これは明らかにポリティカリーインコレクトである。
マルチカルチャリズム(多元主義)を標榜する現代オーストラリアにおいては、公式にこんな見解を示せば間違いなく袋だたきである。
しかし彼女は酔っていた。
「そういう奴らのせいでね、オーストラリアの古き良き伝統もどんどん失われていくのよ。
古き良き友愛関係(マイトシップ)がね。
そうそう、ダメといえばアボリジニという人種は、もう本当にクソッタレよね。
クソの役にも立たない、最低の人種」
彼女はpeopleではなく、はっきりと人種(race)という言葉を使った。
レイシズムのレイス。
「数年前に中国人の留学生の女の子が殺されたのよ。
バスを降りたらアボリジニの男がつけて来て、彼女を茂みでレイプしてから殺しやがった。
奴らはね、二言目には我々は虐げられた民族だ、我々の土地を返せ、とこう来るのよ。
首相が謝罪して、十分な保証を受けているにも関わらずに。
だいたいね、この国はイギリスが植民地にしたからここまで立派に発展した訳でしょ。
近代化に成功したのは私たちのお陰なのに。
もしそうでなかったらね、日本が占領して酷い事になってたはずよ。
日本がかつてアジアでやった事を知ってるでしょ?
それかクソッタレオランダ人が占領してたって可能性もあるわよね」
僕は呆れて言葉もなかった。
論理の飛躍も凄まじいし、あまりに身勝手な歴史認識である。
というか、この人の場合イギリス系以外は全部ブルシットなのかもしれないけど。
確かに現代アボリジニの中には不逞の輩もいる。
街で見かけるやばいめの人々はただでさえ目立つ上に、それがアボリジニである確率が高いので、余計に彼らに対するイメージが悪くなっているのだ。
彼らが都市犯罪の一翼を担っているのもある程度事実だろうけど。
でもね、そりゃあんまりだ。
あんた方にそんな事を言う資格はない。
ファーストフリートがやって来るはるか以前から、ここに住んでいたのは彼らなのだ。
他人の家に勝手にやって来て好き放題やったのはヨーロッパ人の方なのだ。
本来の意味での古き良きオーストラリアの伝統を破壊したのはあんたらだ。
30万人ほどいたアボリジニも、19世紀半ばには実に十分の一にまで激減してしまった。
こんなのは誰がどう考えたって犯罪である。巨大な犯罪だ。10代かけて償ったってまだ足りないだろう。
しかし、僕を最も暗澹たる気持ちにさせたのは、彼女の超ラディカルな意見は個人的なものではなく、イギリス系移民のごく一般的な本音なのではあるまいか?という事だ。
僕はそれまで、ヨーロッパ系オーストラリア人は歴史的にはアボリジニに悔悟と哀悼の念を抱きつつも現実には彼らを疎んじている、というねじくれたジレンマに陥っているのだと思っていた。
でも本当はそうじゃないんじゃないか。
彼らは全く反省なんかしてないし、実を言えば他の有色人種の存在も疎ましく思っているのではないか。
白豪主義の時代からなんにも変わってないんじゃないのか。
帰り際、彼女は「またいらっしゃいね、ダーリン」と言って僕をぎうううっと抱きしめ、派手なキスをしてくれた。
いい人なんだか悪い人なんだかよくわからない。多分いい人なんだろうけど。
ところで、僕が冒頭でアボリジニの男にお金をあげなかったのはちゃんと理由がある。
僕はこれまでにアジアやヨーロッパで様々な物乞いに何度も何度もを声をかけられて来た。多分声をかけやすいのだろう。
相手が小さい子供だったらだいたいあげる。あげたって無駄な事はわかっているけれど。
成人の場合はまずあげない。働けよお前、と思ってしまうからだ。
あげない事で彼らの勤労意欲が刺激される訳ではない事はわかっているけれど。
僕がとっさに取った行為が正しかったのかどうかはわからない。
彼らがアルコールに耽溺するのは構造的な要因によるものだから。
でも、僕が酒代をあげた所で何かが解決するとは到底思えない。
そして、お金をあげてもあげなくても僕は必ず虚しい気持ちになる。自己嫌悪に陥る。
結局のところ、魚が一匹跳ねたところで大河の流れは変わらないのだ。
だから、まあ、昼間っから酒飲んでないで働いてください。
僕だって働いているのです。
21:05:51 |
ahiruchannel |
1 comment |
04 February
そもそもの始まりは
二十歳の夏休みに初めて一人でよその国へ出かけた。旅行社で航空券の手配をし、現地の友達へ国際電話をかけて居候の諒解をとり、パスポートを新しくし、スーツケースを買い、それを引きずって地の果てにあるような遠くの空港まで行き、そして飛行機に乗った。
行き先は西オーストラリア州パース。
そこで何をしたという訳でもなく、ただ毎日本を読み、楽器を弾き、暇を持て余したらちょっとパース近郊をぶらぶらする、そんな生活を一ヶ月ほど続けた。
だからこれはどのような意味合いにおいても旅ではない。
ただ、一人で海外へ出てみたというだけの事だ。



オーストラリアという国の選択にも大した必然性はない。
子供の頃に短期ステイで訪れた事があって、現地に友達がいるというのが唯一の理由らしい理由だった。
こう言っちゃなんだが、オーストラリアというのは基本的にたいへん退屈な国である。
「金の北米〜」というフレーズをご存知だろうか?
古くから日本人パッカーの間で呼びならわされて来た旅の言葉だ。
金の北米、女の南米、耐えてアフリカ、歴史のアジア、ないよりマシなヨーロッパ。
歴代のパッカー達が旅の力点をどこに置いて来たのか、実に簡潔かつ明瞭に物事の本質を突いていると思う。
その文脈でいくと、オセアニアなんかは「論外」という事になるはずだ。
エントリーすらしてもらえない。
10年余の後に、その退屈さを求めて移り住む事になるだろうとは、当時は夢にも思わなかった訳だが。



だが、そもそものきっかけ、つまり僕があっちこっちふらふらと旅ばかりするようになってしまった最初の動機付けはこのオーストラリアという国で起こった。
ある日、友達が水族館へ行こうと誘ってくれた。
異国にあるとはいえ、さすがに僕も代わり映えのしない日々にややウンザリし始めていたので二つ返事でついて行った。
西オーストラリア随一と謳うだけあって、なかなかの規模の水族館だった。
(今はどうなっているか知らないが)パイプ状の水槽が縦横に走り、その中を巨大なサメやエイが泳ぐ。
そして、海洋と直結したプールでのイルカショーが目玉だ。
イルカはよく訓練されており、我慢強く、頭が良かった。(今やオーストラリア中に溢れ返っている某国のろくでもないワーキングホリデーメイカー達よりもよほど頭が良いと、僕は個人的に思う)
元来がひねくれものなので、そういうのを見るとうさん臭く感じてしまうのだが、イルカに罪はない。
総じて、水族館は楽しかった。
でも、言っちゃえばそれだけだ。
水族館が楽しいのは当たり前であり、それが日本以外の場所になくてはならない理由はない。
結局、自分は一体何を求めているのかが分かっていなかったのだ。
漠然とした違和感を感じながらイルカのハイジャンプを眺めていた。


ところが、運命というやつは曲がり角のすぐ向こう側で僕を待ち構えていた。
昼食を食べに入った食堂の天井には世界地図が描かれていた。
それは一風変わった地図で、要所要所に有名な観光地の立体模型が配してあるのだった。
例えば、ヨーロッパとおぼしきあたりには「エッフェル塔」が突き出ており、アフリカ大陸の北部には「ギザのピラミッド」、東南アジアには「アンコールワットのバイヨン寺院」が生えているといった具合だ。
無論中国には「万里の長城」があり、インド亜大陸には「タージマハル」があった。何しろ10年以上前の事なので記憶が定かではないが、結構よくできた精巧なミニチュアだったと思う。
僕はタージマハルの白さにすっかり魅入られ、首が痛くなるまでずっと天井を見上げていた。
そんなものを熱心に見ていたのは僕だけだったようだ。
友達に声をかけられるまで僕の意識は想像力の彼方へと飛翔していた。
その時に、僕がぼんやりと考えたのはこういう事だ。
「そうか。これから俺はこういうものをいくらでも見て回る事ができるんだな」
天啓というような大げさなものではない。雷に打たれとか、はたと悟ったとか、そういう事では決してなく、ただただ茫漠と、世界を旅して回る可能性に気づいた。
今にして思えば、この瞬間が全ての始まりだった。

それから現在に至るまで、僕は何十という国々を歩き回り、憧れのタージマハルやアンコールワットはもちろんのこと、その他多くの物を自分の目で確かめた。
チベットにも行ったし、シルクロードも横断した。
ないよりマシなヨーロッパとは言いつつも、ほとんどの国を訪れた。
なぜそんな風になってしまったかと考えた時、まっすぐに思い出すのは、あの昼下がりの水族館の食堂だ。
あの部屋で僕は世界に出会った。



おっと。
あの言葉には続きがあるのだ。
金の北米、女の南米、耐えてアフリカ、歴史のアジア、ないよりマシなヨーロッパ。
豊かな青春、みじめな老後。
19:04:11 |
ahiruchannel |
2 comments |
23 May
健啖なる旅の胃嚢を充たす為に 3

突然ですが、ここでトリビアクイズです。
世界三大美女といえば、クレオパトラ、楊貴妃、小野小町。
では、世界三大料理といえば?
正解は、フランス料理、中華料理、そしてトルコ料理。
一体誰が何を基準に決めたのかは知らないが、そうらしい、です。
前者二つはよくわかるけど、トルコ料理ってなに?
全然イメージ湧かないんですけど、という向きもおありでしょう。
そんなあなたにお届けする「あひるCHANNELとトルコの幸せな食卓--ただし徹底的にB級グルメのみ」
おっと、読み始める前におやつを用意して下さいね。
かの光源氏の君は自らの涙で枕を浮かべる程だったというが、自らの涎で沈んでしまわぬよう注意して頂きたいものです。
さて、日本料理がスシ、イタリア料理がスパゲッティというように、シンボルとしてのトルコ料理は何だろうかと考えた時に、真っ先に思い浮かぶもの。
それはやはり「ドネルケバブ」ではないだろか。
本来は宮廷料理でありながらファストフードの定番メニューでもあるこのドネルは、トルコ国内のみならず諸外国へも大いに広まっている。
垂直に立てた鉄串に巻きついた巨大な肉の塊が、ぐるぐると回転しながらあぶり焼きにされている様を、あなたもご覧になったことがあるかもしれない。
肉の表面が焦げる香ばしい匂いがあたりに漂い、ジューシーな肉汁が受け皿にこぼれ落ちる。
刃渡りの長い専用のナイフでこれを削ぎ落とし、さらに受け皿の上で細かく刻んで客に供するのだ。
食堂ではつけ合わせと一緒に皿で出てくるが、屋台ならば野菜と共にパンにはさんで食わせるのが一般的だ。
肉にはあらかじめ香辛料やヨーグルトで下味がつけてあるが、最後にマヨネーズ、ケチャップ、チリパウダー等で味を調える場合も多い。硬派に塩をふるだけ、という店もある。
これに大口開けて喰らいつく。
溢れんばかりに具がつまっているので、こぼさないように注意されたし。
うむ。改めて考えるまでもなく、こりゃうまい。
惜しむらくはビールが傍にないこと。
トルコではアルコール類はレストランにしか置いていないので、屋台や庶民の為の食堂ではまず飲めない。
これでキリッと冷えたビールがあれば人生は完全無欠の薔薇色なのだが、何もかもうまくいく訳ではない。
そこで、代わりと言ってはなんだが「アイラン」を飲む。
アイランとは塩味のついた液体ヨーグルトのこと。
さしずめ、MEIJI飲むトルキッシュヨーグルトといったところか。
日本ではヨーグルトは甘いものと相場が決まっているので、最初は面食らうのだが、これが意外なくらい肉料理に合う。
飲み慣れると病みつきになり、やがては食事の際にアイランがないと何か物足りないということになってしまう。

ドネルケバブは大まかに白と黒に分かれる。
店先で回っている肉塊が白ければ、それは鶏肉。黒ければ牛肉か羊肉だ。
路地裏にあるような小さなスタンドではどちらか一種類だけ、やや規模の大きい店では豪快に白黒両方が回っていたりする。
僕自身の好みで言えば、ドネルは断然羊肉に限る。
羊は臭いと敬して遠ざける人も多いようだが、肉は臭いからこそうまいのではないか。
チーズと同じだ。強烈な癖のあるナチュラルチーズの方が、どこか画一的なプロセスチーズよりも何倍も深い味わいがあるように思う。
羊と牛のドネルは一見して見分けがつかないので、僕は観光地を避けて地元民しか行かないような店で食べるようにしていた。傾向として羊率が上がり、値段は下がる。
ちなみにドネルスタンドは肉が無くなり次第営業終了だ。
朝はあんなに大きかった肉の塊が、夕方近くになるとやせ細って鉄串にわずかにへばりついているだけ、という状態になる。
僕はそれを見るたびにえもいわれぬ寂寥感にとらわれるのだ。
それが人生の黄昏を連想させるからだろうか。
あるいは単に腹の減り始める頃に肉がないことの哀しさか。
その他、串にささった焼肉であるシシケバブ、スパイシーなつくね串のアダナケバブ、ヨーグルトソースをかけて頂くイスカンダルケバブなども食堂で気軽に食べられる定番メニューだ。
ところで、ケバブは焼き物全般の総称であり、肉料理だけを指すのではないということを最近知った。
街頭には焼き栗売りがたくさんいて、売り子のおっさんが大声で栗ケバブいらんかねえ!と呼ばわっているのを聞いたからだ。
だから焼き魚も当然ケバブ。
という、完璧な前ふりで次にご紹介するのが、ガラタ橋名物、鯖のケバブ。
金角湾にかかるガラタ橋は旧市街と新市街を結んでいる。
正面に見えるのがガラタ塔で、コンスタンティノープルが陥落する以前、この辺りはジェノヴァ人の居留区だった。
エミノニュの波止場からはアジアサイドへのフェリーが発着し、近くにはエジプシャンバザールもあるという賑やかな場所だ。
僕はこのガラタ橋が大好きで、日に一度はスルタンアフメット地区から散歩がてら足を延ばす。
ボスフォラス海峡に釣り糸を垂れる人々、新鮮な魚を商う市場に住み着いた猫たち。
蒼い空をウミネコが行き交い、遠くスレイマニエジャミイの偉容を望む。
ここはイスタンブールが最もイスタンブールらしい場所かもしれない。
魚を焼くよい匂いがすると思ったら、それが鯖のケバブだ。
ドネルと同じくパンにはさんで食べるので、日本人旅行者の間では「サバサンド」の愛称で有名。
鯖の切り身がいくつも並んで炭火であぶられている情景は、心躍るものだ。
塩とレモンをかけるだけのいたってシンプルな味付けだが、脂が乗っていて本当に美味しい。
背骨は売り子が器用に取ってくれる。
ここに醤油がありさえすれば、と考える日本人は多いらしい。
かの深夜特急にもこのサバサンドは登場する。
長い旅の中で、日本から距離的にも時間的にも遠く隔てられてしまった筆者が、このガラタ橋でまた日本に近づいているような錯覚にとらわれるというくだりだ。
海を見たというだけで。魚を食べたというだけで。
ガラタ橋でもう一つよく見かけるのが、ムール貝の「ドルマ」売りだ。
ドルマというのは詰め物料理のことで、ナスやピーマン、トマトに肉を詰めたものがポピュラーだが、これはスパイシーなピラフをムール貝に詰め直したというもの。
直径50センチくらいの銀色のたらいにムール貝が積み上げられている。
売り子のおっさんに1リラコインを渡すと、貝殻を二つに割ってレモンを絞ってくれる。
それを一口でほおばる。
ムール貝の甘みと、米の胡椒っ辛さ、レモンの酸っぱさが渾然一体となり口中に広がる。
もぐもぐやっている内にもう一つ手渡される。1リラで2個食べられるのだ。(ツーリストエリアを離れると3個食べられる場合もある)
食べ終わったら紙ナプキンのサービス。
たった1リラでこれほど豊かな気持ちになれる食べ物も珍しい。
地元人もしょっちゅう立ち止まってはパカパカ食べている。だって美味しいもんね。
炊き込みご飯というところが日本人の感性にもマッチしているように思う。

もうひとつ。
手軽に食べられる庶民派メニューとして「ピデ」をおすすめしたい。
小麦粉で練った細長い舟形の生地にひき肉やサラミ、トマトなどの具を乗せ、上からチーズをかけて石焼釜で焼き上げる。
ピデ専用の食堂もちゃんとあって、そういう店ではオーダーしてから生地を伸ばし始める。
焼きたて熱々のピデは大きすぎて皿に乗らないので、幾つかの断片に切り分けてくれる。
美しくとろけるチーズ。肉とトマトソースの奇跡的な邂逅。
しかしあくまでもB級グルメ。
ご想像の通り、これはイタリアのピッツァと全く同じコンセプトの料理だ。
いわばトルコ式ピッツァ。
あるいはピッツァがイタリア式ピデなのかもしれない。
どちらがオリジナルなのかは浅学にして知らないが、ピデもピッツァも共にギリシア語の「ピタ」を語源とするらしい。
ちなみに、トルコにはマントゥという名の料理もある。
漢字を当てるなら当然「饅頭」ということになろう。
これはヨーグルトソースがけラビオリ風といった一皿だが、小麦粉生地の中に具を詰めるという様式は饅頭に通底する。

お腹がくちくなったところでお茶にしよう。
チャイ。
トルコの旅はチャイに始まりチャイに終わる、と誰かが言ったかどうかは知らないが、とにかく一日に何杯も飲むのは確かだ。
朝はもちろんチャイと共に始まるとして、店に入ればまあ座って一杯、フェリーの待ち時間にスタンドで一杯、昼食後にまた一杯、午後のおやつでもう一杯、長距離バスの中でもどうぞ一杯、という風に際限なくチャイが登場し続ける。
まるで利口な仔犬が傍に控えているかのように、日常のあらゆる場面で、そこにチャイはある。
真ん中のくびれた可愛らしいチャイグラス、受け皿に角砂糖は2個。
グラスが熱くなっているので、ふちをつまんで、すするように飲む。風情がありますなあ。

一般に大陸アジアは茶の文化圏だと言われている。
中国はもちろんお茶大国。
人民はマイ湯のみを常に携帯し、お湯さえ手に入ればいつでもどこでもすぐに茶を淹れる。
今回、中央アジアでも緑茶が飲まれるということがわかった。日本茶にそっくりなので、なんだか嬉しくなってしまう。
インドではチャイと言えばミルクティーのこと。
ガンジス川のほとりでチャイを飲み旅情に浸る。
で、そのグラスを川の水で洗っているのを見てぐえっとのけぞるのもまた楽しい。
腹壊しても知らんけどね。
ネパール、パキスタンも同じくミルクティー。
ネパールのチャイは生姜がきいていて濃厚。
イラン、トルコはプレーンティーだ。
トルコではチャイグラスの中に砂糖を入れるが、イランでは角砂糖を口に含み、溶かしながら茶を飲む。
これがなかなかに熟練を要する技で、初心者は一杯のチャイで角砂糖を何個も消費してしまう。
ダイエット中の婦女子はイランには行かない方がよろしかろう。
チャイを飲みながら茶菓子にも手を伸ばそう。
「バクラヴァ」と呼ばれる伝統的なパイ菓子の蜂蜜漬け。
フォークで切ろうとすると中から蜜がとろりとしみ出してくる。
甘い。この上なく甘い。
この甘さが病みつきになってしまうのだなあ。
ピスタチオ入りやらチョコレート味やら色々とバリエーションがあり、見た目にも楽しい。
イランでもよく見かける「トゥルンバ」という小さな棒ドーナツもやはり蜜漬け。
口の中でさくさくの皮が決壊し、中から蜂蜜が流れ出す甘美なる瞬間よ。
ダイエット中の婦女子はトルコには行かない方がよろしかろう。

庶民のための食堂は「ロカンタ」と呼ばれる。
カフェテリア形式になっていて、店頭にディスプレイ用のガラスケースがあり、欲しい料理を指差しで選べるのだ。
定番はやはり煮込みか。
羊肉や、ナス、芋、豆などをトマトで煮込んだ料理。
付け合せの「ピラウ」は米を油とスープで炊き上げたもの。
中央アジアではこの種の米料理は「ポロフ」と呼ばれていたが、どちらも「ピラフ」と同じ語源を持つであろうことは容易に理解できる。これは美味しい。
肉料理としては、羊肉のハンバーグである「キョフテ」が大変いける。
焼きキョフテに煮込みキョフテ。
キョフテ専門店もあるくらいで、トルコ人も大好きな一品だ。
バルカン半島ではこれと同じものが「コフタ」と名を変える。
その昔、オスマントルコが半島を支配していた時代に伝わったのだろうか。
インドにもコフタはあるが、こちらは肉に限らず団子状のものの総称のようだ。
心ときめく、素晴らしき料理の数々。
だが、僕が最も好きなのは実は朝食なのだ。
平均的なトルコ朝食の内訳は、チャイ、パン、キュウリ、トマト、黒オリーヴ、白チーズ、ゆで卵、となる。

チーズは単体で食べるとちと塩辛いが、トマトと一緒に口に入れるとちょうど具合が良いことを発見した。
イタリアの前菜でトマトとモッツァレラチーズのサラダがあるが、あれにヒントを得た。
キュウリはあくまで瑞々しく、オリーヴ、卵もそれぞれに美味しい。
が、主役はあくまでもパンだ。
フランスパンをもっとずんぐりとさせたような形をした「エキメッキ」と呼ばれるこのパン、これがトルコの食生活には欠かせない。
どのロカンタでもエキメッキは無料でついてくる。
各テーブルには輪切りのパンが大量に入ったバスケットが置かれており、これは好きなだけ食べてよい。お代わりも自由。
エキメッキは法律で販売価格が一律に定められていて、ひとつ1リラもしないくらい安い。
僕はどこの国のパンよりもこのエキメッキが好きだ。
外側はパリッと香ばしく、内側はふわふわで口当たりが非常に軽い。
これにバターと蜂蜜をたっぷりとつけて食べるのだ。
バター&ハニー。
僕はかねがね思っていたのだが、この組み合わせを考え出した人にはノーベル平和賞を授与するべきではないだろうか。
(あと、明太子とパスタを組み合わせた人にもあげて欲しい)
バターと蜂蜜は見事なまでにエキメッキによく合う。
僕はすっかり浮かれてしまって、毎朝毎朝、気づくと巨大なエキメッキ一本をすっかり平らげてしまっているという有様だった。
この朝食を屋外で食べられれば最高だ。
4月の朝はやや肌寒い。
風を感じながら、温かいチャイグラスを手のひらに包み込む。
テーブル脇の樹木から花がはらはらと舞い落ちる。
チャイにも花が浮かぶ。
宿の親父は恐縮して詫びるが、そうではない。
日本人はこういう風情を好むのだよ。
時間はあくまでゆるやかに流れる。
あれ?
もしかしてこれは幸せというやつではないか?
さわやかな風と、一杯のチャイ、パンとバターと蜂蜜があればいい。
それだけで人生はかくも豊かなものになり得るのだ。
そう思わせるものが、トルコの朝には確かに存在する。
事ほど左様に、トルコの食卓は幸せなのであります。
毎日が幸せの繰り返し。
それは人々の胴回りにもはっきりと現れる。
トルコの若者は男女ともに美しい。スタイルも抜群。
それが、人生のある分水嶺を越えると、皆が皆、判で押したように同じ体型になってしまうのだ。
セイウチ。トド。
これは民族の血か?
それとも幸せの代償か?
ま、いいか。
ダイエットなんか明日からすればいいんですよ。
09:51:26 |
ahiruchannel |
2 comments |
12 April
健啖なる旅の胃嚢を充たす為に 2
結局、中国の旅はちょうど1ヶ月間だった。雲南省でしばらくごちゃごちゃとやって、その後シルクロードの起点である西安に移動。
河西回廊、新疆ウイグル自治区と進み、カザフスタンへと抜けた。
そのカザフの旧都で理不尽な災厄に次々と見舞われた訳だが、あまりにも恨み深く、書くことも多いので、次回に回す。
それよりも、忘れない内に中国の旅を総括しておきたいと思う。
総括と言っても、アレではないよ。
誰かを拉致って集団で暴行を加えたりとか。
自己批判せよ!とかね。
先にも書いたように、中国という国は本当に無茶苦茶な所である。
文化民度はもう信じられないくらいに低い。
国中どこへ行ってもごみだらけ、人々はそこかしこで痰を吐き散らし、のべつ煙草を吸いまくる。
公衆トイレは想像を絶する世界。
車の運転はすこぶる荒く、信号なんか誰も守っちゃいない。
人より車優先の感があり、ひき殺されないように常に注意していなければならない。何しろ歩道だろうが何だろうが猛スピードで突っ込んで来るのだ奴らは。
割り込みなんかは朝飯前。毎日誰かしらにぶつかられ、押しのけられ、いつまで待ってもものが買えない。
確かに急速に経済発展しているのはよく分かるのだが、それに民度が全く追いついていないのだ。
よくもまあ、こんな国でオリンピックなんか開こうと思ったものである。
200年は早いという気がする。
当局は躍起になって北京市内の人民のマナー向上を指導しているらしいが、きっと無駄だろう。
TVでも白々しいマナー啓発コマーシャルをよく見かけるが、要するに、お上主導でそういうことをしなければならないほど民衆の意識は前近代的なのだ。
ま、何しろ人の数が多すぎるからね。
他人に遠慮して慎ましくやってなんかいたら、あっという間にうつ病になってしまうのかもしれない。
オリンピックはどうかTVだけで観戦されることを強くお勧めする。
さて、散々こき下ろしておいて何だが、今回は中国の悪口を書くのが目的ではない。
おいしい、楽しい、ご飯の話をしよう。
ここで、このブログを読んで頂いている方々に大変な告白をします。
僕は、1ヶ月の間、中華料理以外のものを、一切口にしていない。
うむ。
我ながら阿呆ではないかとも思うのだが、紛れもない事実である。
朝、昼、晩。す・べ・て・中華。
それを30日間。
スーパーサイズミーを地で行く無謀っぷりだ。
土地によっては、ペー族やウイグル族の料理なども食べたが、味に大差ないので便宜的に中華料理に含める。
文化人類学者じゃないからね。
当たり前と言えばこれほど当たり前の話もないのだが、中国で食べる中華料理は滅法うまい。
なおかつ嘘みたいに安い。
1日2〜3食で平均30元ほど使っていたが、邦貨にして450円程度か。
もちろん、僕がバックパッカーであるという事情はある。
フカヒレとかアワビとか、北京あひるとか、そういうものを高級レストランで食べればすぐに100$200$と使う羽目になるだろう。
あくまで現地人しか行かないような(きったない)大衆食堂の話である。
そんなんでお前、腹は壊さなかったのかですと?
壊しました。壊れっぱなしです。
新しい街に行く。その土地のものを食べる。腹を壊す。それでも構わずに食べ続ける。
すると、胃腸が適応するのか3日目くらいから調子がよくなる。
だが、次の街へ移動するとまた腹を壊す。
僕にとって、長旅とはその果てのない繰り返しである。
飲み水だけはミネラルウォーターを買うようにしているが、後は格別に気を遣うということはない。
食堂で茶が出ればごいごい飲むし、市場でキュウリを買ったら水道水でざぶざぶ洗ってそのままかじる。
歯磨きもタップウォーターでやってるしね。
話を戻そう。
そのようにして、朝から晩まで中華料理を食べまくっていた訳だ。
雲南省では、朝、昼は主に麺類を食べた。
日本でいうところのラーメン、つまり小麦粉麺は面条といい、米の粉で作った麺はミーセンという。
どこの食堂でも牛肉面、酸辣面などの基本的な麺を出した。
ミーセンはこの辺りの名物なのだが、ぷつぷつとすぐに切れてコシがないので、僕は面条の方が好みだ。
場合にもよるが、何も考えずに麺を頼むと大抵は赤いスープに浸かって出てくる。
辣。つまり辛いのだ。
それを起き抜けにひいひい言いながらすすり込む。鼻水も涙も一緒になって垂れ流し。
安食堂のテーブルには必ずトイレットペーパーが設置してあるが、それにはちゃんと理由があるのだ。
この麺はだいたい5元が相場。100円しない。改めて考えるまでもなく、阿呆みてえに安い。
夜はいわゆる中華料理とされるものを食べた。
麻婆豆腐、青椒肉絲など、メニューに見知った漢字が並んでいる。
そういう親しみのある料理から始めて、毎晩違う皿にチャレンジしていった。
何を注文しても本質は同じ。
肉、野菜を多量の油で炒め、「中華味」がつけてあるのだ。
僕は中華が大好きなので、コテコテ、ギトギト、ドンと来い、である。全く苦にならない。
おかず1品、米飯、ビール大瓶1本。
どの店でもこういう頼み方をした。
ちょっと高級志向の店だと(と言ってもたかが知れてるが)1皿しか注文しねえのかよ?という目で見られることもあったが、これはまあ当然だろう。
人民は必ず複数でやって来て、いくつも皿を取って、盛大に残して帰るからだ。
我々とは違って、勿体ないという発想がないのだと思う。
もちろん料理は極めつけに安い。
1皿が8〜15元、米飯1〜2元、ビール5〜7元。
毎晩300円ほどの豪華な晩餐だ。
「お通し」として、ひまわりやかぼちゃの種を出す店もある。
人民はこぞって手を伸ばしては、それらをポリポリとかじる。種の皮は床に捨てる。
あれは料理が出てくるまでの空腹をしのぐ為ではなくて、単に暇を潰しているのではないかという気がする。
そう思って改めて周りを眺めると、人民は国中どこへ行ってもしょっちゅうひまわりの種をかじっていることに気づく。
列車やバスでの長距離移動ではこれが必需品。
自らの席に着くやいなや、何はともあれひまわりの種が入った袋が登場する。
それを皆でポリポリ、カリカリ。全員で暇潰しをしている訳だ。
これはそこいら中にハムスターがいるようなもので、床という床はすぐに種の皮で埋め尽くされてしまう。
この打ち捨てられたひまわりの種の皮は、もうあらゆる場所で目にした。
前述の食堂や公共輸送機関はもちろん、道端で、公園で、便所で、宿の部屋で。
僕は自室の床に種が撒き散らされているのを見る度に、ため息をつきつつ、脚でベッドの下に払わなければならなかった。
何を食べてもうまかったが、一度だけ失敗した。
ひき肉の辛い炒め物という意味の料理だったのだが、輪切りの唐辛子が200本分くらいぶち込んであって、一口食べるごとに涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。
うまさに感動した訳ではもちろんない。
結局1/3も食べられずに退散する羽目になったのだが、なめていると時々こういう目に遭う。
続いて西安に移動。
料理も様変わりした。
夜行で着いたので、早速朝飯に麺を食べに出た。
同じ牛肉面でも雲南のものとはまるで違い、幅広のキシメン状。
午前中はあちこちの店先で積み上げられた蒸篭が景気よく湯気を立てている。
肉まんと餃子である。
肉まんは包子、バオズと呼ばれ、可愛らしいミニサイズ。
底面の直径は2.5cmくらいで、8個から10個を蒸篭ごと出してくれる。
酢醤油につけてホクホクといただくと、口中に肉汁の味わいが広がってゆく。朝から幸せな気分になる。
これで3元。45円。
神戸は元町の南京町に有名な行列のできる肉まん屋があって、僕もよく通っていたのだが、ここでは同じサイズのものが1個80円だったか。
これだから貧乏旅行は止められないってんだ。ははは。
日本では中国から輸入したこの食品のせいで大騒ぎになったそうだが、僕は当該国を呑気に旅行中で、ことの顛末を何も知らなかった。皮肉なものだ。
そう、餃子。
蒸餃と水餃の2種類があって、どちらもよく食べた。
水餃はスープに麺の代わりに餃子を入れましたという具合で、ボリュームたっぷり。大変おいしい。
これの亜種で、砂鍋水餃という料理もある。
鍋でぐらぐらに煮立てたスープに餃子が潜んでいる。
鍋で出す必然性があるのかどうかはともかく、これもいける。
ちなみに、焼き餃子はただの一度も見かけなかった。
さらに新疆ウイグル自治区へと進む。
ここらは東テュルキスタンとでもいうべき土地であり、チベット同様、中国に含めるにはかなり無理がある。
ウイグル人は顔つきも言葉も漢族とは全く違う。
社会の仕組みもより共同体的、かつバザール的だ。
街中ではずんぐりしたウイグルパンやケバブを商う屋台をよく見かける。
だが、中華との混血料理もある。
例えば、包子(新疆ではボウズと発音される)は、この地でもポピュラーな料理だ。
ウイグル人の店に入ると、中身が羊肉になるのがいかにもお土地柄。
彼らは、清心、つまりはムスリムなので豚肉は口にしないのだ。
味付けは中華に近いが、よりスパイシーになる。
酢醤油につけて食べるのは同じ。シルクロードと中原のクロスオーバーである。
その他、僕が好んで食べたのは拌面という料理だ。
ウイグル語ではラグマンと呼ぶ。
ぶっかけ皿うどんとでもいうべきもので、太めの小麦粉麺に肉野菜炒めをかけていただく。
この麺料理の比類なき美点は、注文してから職人が麺を打ち始めることだ。
小麦粉の塊をバンバンと打ち付けていると思ったら、見る間にばらばらとほぐれて麺になってゆく。奇術でも見ているかのようだ。
それを大鍋で湯がいている間に、別の調理人が中華鍋をふるう。
最後に皿にあけられた麺に、たっぷりと具をかけて出来上がり。
これは掛け値なしにうまかった。
毎日2回ずつ食べたほどだ。当然腹を壊した。
なぜそんなにも拌面に魅了されたかということだが--ここからが本稿で一番大事なところだ--この麺、フィギュアもテクスチュアも、あの讃岐うどんに酷似しているのである。
僕は毎年高松近郊へのうどん詣でを欠かさず行い、内地ではカトキチの冷凍讃岐うどん以外、うどんと名のつくものは一切口にしないという自他共に認める硬派だ。
それが、中国の端っこで、こんな素敵なうどんに出会えるなんて。麺文化は偉大だ。
余談だが、このウイグル風ラグマンは周辺諸国でも食べられる。
それで、カザフスタンに入ってから一度だけ試してみたのだが、どうしようもなく不味かった。
ラジアルタイヤの細切りに醤油をかけてあるのか?
やはり、中華との混血という所にポイントがあるらしい。
飯がうまく、しかも安い。
それは文化が豊かな証左である、というのが僕の持論だ。
食に心血を注ぐ民を、そして彼らの食を僕は愛する。
わざわざ辺境の地へ出かけて行って、その土地の美味しい一品にめぐり合う。
これは案外旅の本質かもしれない。
誰かが言っていた。海の味を知るには、一滴飲めば十分なのだと。
それにしても、中国のこの圧倒的に豊かな食の創造性、感性と、人民のモラルの低さがどうしても結びつかない。
不思議な国である。
おまけのエピソードをひとつ。
昆明では茶花賓館というパッカーの間では有名なユースホステルに泊まった。
ユースらしく情報ノートなんてものも置いてある。旅の知識やお役立ち情報を皆で共有しようという訳だ。
真に有益な情報から、便所の落書きのようなものまで、中身は種々雑多。
そのノートにこんな書き込みを見つけた。
どこの国の旅行者かは失念したが、英語の記述だったので白人パッカーだろう。
CAUTION!という書き出しでそれは始まる。
やあ、みんな。
この近くにある「ママフーレストラン」には気をつけた方がいいよ。
僕たちはそこでハワイアンピッツァを食べたんだけど、次の2日間、ベッドとトイレを往復する羽目になったからね。
だいたい、ここのピッツァは小さいし、その割に値段が高いし、たいしておいしくもないし、お勧めしないよ。
異国の地で腹痛で大いに苦しんだという点は同情に値しなくもない。
うむ。
でもなあ、やっぱりこいつらは阿呆ではないか?
どうして雲南省くんだりまでやって来て、わざわざピッツァを、それもハワイアンピッツァなんてものを食べなきゃいけないんだ?
うまくて安い地元の食がこんなにも充実しているというのに。
偏見100%で言わせてもらうが、白人ツーリストにはこの手の阿呆が多い。特に東南アジアではよく見かける。
ツーリスト向けのカフェに群れ集って、ビール瓶を何本も空にし、馬鹿騒ぎしながら、フライドポテトとか、グリルドチキンとか、パンケーキとか、そういう安直でしょうもないものをツーリストプライスで食べている連中だ。
ヴェトナムやタイ、ラオスまで来てなぜにパンケーキを食べる貴様ら?
そういう連中が大勢来るからこそ、ツーリストエリアが形成され、安宿やネットカフェが作られる訳だから、非難ばかりはできないのだが。
ま、他人のすることだから別にいいけどね。
という訳で、北京オリンピックは、ほかほかの肉まんをつまみながら、あるいはひまわりの種をぽりぽりとかじりながら、TVで観戦していただきたいと思います。
20:02:20 |
ahiruchannel |
10 comments |
14 February
旅人交遊録
タイからラオスへの国境越えのバスで出会ったおじさんの話。昭和24年生まれの丑年。僕の両親と同い年で、還暦前である。
前歯が二本なく、他の歯も銀歯だらけ。
そのせいか発音がやや不明瞭で、しゃべる言葉は隙間風のよう。
お店で何かをオーダーする時も、店員は彼が何を欲しているのかなかなか聞き取れない。
そんな時には僕が大きな声で復唱してあげなければならない。
さて、このおじさんは何者か?
一目見てカタギではあるまいなあ、と判断する。
あまりにもくたびれているし、旅慣れ、いや旅ずれしているようにさえ見える。
アジアでは(特にタイ周辺では)こういう崩れた感じの年配の旅行者を割によく見かける。
東南アジアが好きで通ってる内に段々と深みにはまり、女を作り、やがては住み着くようになり、観光ビザを更新する為に定期的に隣国へ出かけることを繰り返す。そういった手合いだ。
しかし、お休みで来ておられるんですか?と訊ねる。
一応。儀礼上。全然そんな風に見えなくてもね。
だって普通のいい歳した日本人はバックパッカー用のツーリストバスになんか乗らないですよ。
返って来た答えは…。
いえ、私はね、旅が仕事なんですよ。
まあ。素敵なお言葉。
物でも書いているのだろうか。それとも写真?
いやね、私、虫採ってんですよ。もう30年続けてます。
ほう、虫ですと。
ドクトルマンボウ昆虫記の虫。なんとお珍しい。
マンボウ氏と密かに命名する。
僕は彼と部屋をシェアすることにした。
マンボウ氏はお酒をこよなく愛する。
宿に荷物を降ろしたら早速酒屋を探しに行ったし、焼酎の無料サービスがあるという理由で地元民しか行かないような焼肉屋へ連れて行かれたりもした。
(夕食を終えて部屋に帰って来ても、まだ一人で飲み続けていた)
その焼肉屋でのこと。
どこの部位だかまったく怪しい肉をつつきながら、問わず語りに身の上話を始める虫採り男。
グラスを満たす琥珀色の液体は「ラオラオ」という地元の酒だ。
多分米でできているんだろう。
それをちびりちびりとやりながら、虫の話をしてくれる。
氏の狩猟場(というか何というか)は主にインド、中国、そしてアフリカ。
獲物は蝶、トンボ、他にセミなど。
それらを標本にして、蒐集者に売るのが仕事である。
蝶と言っても、土産物屋でみかけるような大きい派手なものではない。
氏に言わせれば、あんなのは「つまんない」ということらしい。
彼が追うのはもっと小さくて地味なものである。
つまり玄人好みの希少種を狙う訳だ。それを学者やマニアに提供して、報酬を得る。
やはり30年も蝶を追っていれば新種を発見したりすることもあるのだろうか?
ありますねえ。全くの新種はひとつですけど。私の名前がついてますねえ。
あとは亜種が4,5種類くらいですか。
何しろヨーロッパ人が植民地時代にほとんどの種を見つけてしまってねえ。
新しいのはなかなか出ないんですよ。
昆虫の蒐集というのは、いわば古本マニアと同じで、まったく一代限りの趣味なのだそうだ。
本人が死んでしまったら、家族にとっては虫などガラクタでしかない。
しかも標本箱というのは出鱈目に大きいものだから、せっかく体系だてて集められた虫たちも二束三文で売り払われて散逸してしまう。
氏も貴重な標本をいくつか持っており、できれば博物館に寄贈したいのだが、どこも満席で受け入れてくれないのだとか。
昔は学者に提供してましたから。
学術貢献しているという自負も少しはありましたがね。
バブルがはじけてからは駄目ですね。大学の教授なんかお金ないもの。
今の客筋は医者とかですねえ。標本マニアのお医者。
マンボウ氏の仕事は時に違法行為となる。
何しろその国の山野に勝手に入って行って、勝手に虫を採っているのだ。
いわば密猟。
捕まったことも何回もありますよ。
刑務所にも入りましたよ。スリランカだったかなあれは。
留置所と裁判所と刑務所をたらい回しにされて、何週間か出てこれなかったですねえ。
地元の新聞とかテレビにも大きく報道されたみたいですよ。
日本の新聞にも小さく載ったらしいけどねえ。
マンボウ氏はいわゆる団塊の世代である。
学生運動には当然深く関わったし、勤めてからは(勤めていた時期があったのだそうだ)組合運動に精を出した。
今でも政治的にはなかなかラディカルな思想を持っている。
そして虫を採り始めて30年余。
気がつけば還暦を迎えるような歳になった訳だ。
繰り返しになるが、我が父母と同じ年に生を受けた人である。
そしてちょうど今の僕くらいの年に虫採りの旅を始めた計算になる。
波乱万丈とは言わないまでも、相当に変わった人生ではある。
今はもう必要な分だけしか採らないですね。
昔は両手にダンボール抱えて日本に帰ったものですけどねえ。
もう無駄な殺生はしたくないんです。
命あるものをこの手で殺めることが段々辛くなってきてね。
退職金なんてないから、70まで勤めてすっぱり止めるつもりです。
子供もみんな独立したし、まあ安心ですよ。
隠居して読書三昧の日々を送るのが夢ですね。
でも旅でおたくみたいな若い人と出会うのが楽しくってねえ。
なかなか止められないかもしれないな。
その日の真夜中。
酩酊してそのまま寝入ってしまったはずのマンボウ氏が突如壁を叩きだした。
おい、ここはどこだ?
俺はどこにいるんだ?
僕はあわてて部屋の灯りをつける。
大丈夫ですか?
僕の顔を見て安心したのか、便所に立つマンボウ氏。
刑務所に入れられた時の夢でも見たのだろうか。
そういえば欠けた二本の前歯は捕まった時に折られたのかもしれないな、とふと思い当たった。
00:02:04 |
ahiruchannel |
2 comments |