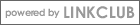30 January
上を向いてゆっくり歩こう
隣席の韓国人と思しき若者が尖った声をあげる。おい、オーダーした、すでに、30分!
かなり怪しい英語だったが意味は十分に伝わる。
確かに彼らが料理をオーダーしてからかなりの時間が過ぎていた。
その時、僕は道端に簡易テーブルと椅子を出しただけの路上食堂で、獅子のロゴの入ったビール瓶を傾けていた。
旅行者で溢れるカオサンロードから一本隣の路地。
向かいの店からはライブ演奏が聞こえてくる。
ギターの伴奏にあわせて、タンバリンをふりながら女の子が「クロスロード」を歌っている。
ここ何年か、カオサン周辺では生演奏を聞かせる食堂がずいぶんと増えた。
ホテルカルフォルニアだとか、ティアーズインヘヴンだとか、そういう誰でも知っているような無害で偉大な名曲が至るところで毎夜繰り返される。
狭い路地をタクシーやトゥクトゥクがひっきりなしに行き交い、少数民族の衣装をまとった老婆が蛙の鳴き声が出る玩具を売り歩く。
両足のない男が地面をはいずりながら客にお恵みを求めているかと思えば、スピーカーとアンプを背負った盲目の男がタイ演歌を歌いながら徘徊している。
ビールを飲みすぎた連中が馬鹿声を張り上げて笑っている。
路上にガスボンベとコンロを置いただけの簡易厨房から煙がもうもうと上がる。
いつもながらの混沌とした、いかにもカオサンらしい風景である。
あと何分でできるんだよ?
10分以内に持ってこなかったら金は払わないからな!
二人組の韓国人の眼鏡をかけた方がウェイトレスの女の子に真剣な面持ちで怒鳴る。
彼女は彼女で、仕事にかける熱意や誠意などは微塵も持ち合わせていない様子で、10分ね、オーケーオーケーと軽く受け流す。
僕はそんな光景を微笑ましい思いで眺めていた。
いかにも旅慣れしていない様子が新鮮でもあった。
彼はまだシステマティックで効率優先の韓国時間を振り切れていないのだ。
せっかくリラックスを求めてタイにやってきたというのに。
いや、僕もまた日常の雑事に追われ、知らず心身をすり減らしながら生きている一人なのかもしれない。
タイに来てからというものやたらと人にぶつかりそうになるのだ。
狭いソイを人ごみを掻き分け掻き分け歩いていると、決まって誰かが道をふさぐ。その度に軽い苛立ちを覚える。
歩く速度が周りと違うのだと気づくまでにしばらくかかった。
タイの人々は誰も急いでいない。
いや、中には急いでいる人もいるのだろうが、僕とは歩き方が根本的に違う。
せっかくリラックスを求めてタイにやってきたというのに。
おい、あと2分だぞ!
自らの腕時計を示す韓国人を横目で見ながら、僕は思う。
自分だったら何分待たされたら怒り始めるだろうか。
1時間くらいが限度だろうか。
いや、僕だったらウェイトレスを怒鳴りつけるような真似はしないな。
黙って店を出て、隣の店で注文し直すだろう。
どうせどこの店でも同じ様なものしか出していないのだ。
焦ったっていい事なんか何もない。
明日からはもっとゆっくりと歩こう。
そう決める。
それにしても、頼んだ料理が全然出てこないよな。
17:22:05 |
ahiruchannel |
No comments |
29 November
旅に棲む日々 3
パキスタンでのおはなし。その二。インド国境に程近い街ラホールから、バスに延々と揺られ、車中2泊3日でイラン国境への拠点となるクエッタまで至る道のりについては前回のおはなしをご覧ください。
どうにかこうにかクエッタまで辿り着いた僕は、さらにその夜のバスでイラン国境へと向かう事にした。
結構な強行軍なのだが、勢いがついてしまうという事態は往々にしてあるものだ。
特に移動中の環境が酷い場合には割とやけくそ気味になって、こうなったらどんどん前へ進んでやるさという気分になるのだ。
パキスタンのバスは酷い。移動というよりは穏やかな拷問に近い。
ちなみに、僕が今まで乗った中で一番酷かったのはネパールのカトマンドゥからインド国境へと向かうバスだった。
どれくらい酷いかというと、巨乳だというから期待してはるばる来てみればただのデブじゃねえかこのやろというくらい酷い。
これについては、またいつか書きたい。
それとは別に、当時はイラク戦開戦前夜のきな臭い雰囲気が横溢しており、あまりパキスタンやイランに長居していると何に巻き込まれるか分かったもんじゃないというような事情もあった。
今にして思えば、ラワールビンディもペシャワールもフンザも、パキスタンらしいものを一切見ずに素通りしてしまったのはたいそう勿体ない事だったのだが。
とにかく。
旅行書などには、クエッタからイラン国境へはバスか列車で行くべしと書いてあるので、ほんの隣町くらいなんだろうと思っていたのだが、これがとんでもない。
クエッタ以西は広大な砂漠が広がっており、国境線はほとんど何もない不毛地帯の真ん中に引かれているのだ。
バスは一晩かけて砂漠を横断する。
そんな国境行きのバスでのこと。
夕暮れ時。
バスの乗車を巡ってちょっとしたトラブルがあったのだが、何とか目的のバスに乗り込む。
隣の席の青年は、民族服ばかりのパキスタンには珍しくポロシャツにジーンズという出で立ちで、髭も剃っており、どことなく知的な風貌だった。
英語もなかなか達者で、これからイラン、トルコ、東欧などを経由して北欧に働きに行くのだという。
ヨーロッパはいいよ。この国と違って自由だからね。
金も酒も女も、何でも思いのままだよ。問わず語りにそう話す青年。
そういうものだろうか。
この国では確かに酒は御法度、公共の場で男女が一緒になる事もあり得ない。バスの車両は男性用と女性用に別れているし、そもそも出歩く女性はほとんどいない。
良いとか悪いとかではなくそういう文化だという事なのだが、まあ気持ちはわかる。
バスは少し走っては停車して客を拾う、また走っては客を拾う、というのを繰り返しながら、夕闇迫る街をぐるぐると回った。
アジアのバスというのはだいたいがこの調子で、街から幹線へ出るのにえらく時間がかかる。
おまけに、乗って来る客はすべからく大荷物を抱えているので、それを積むのにもえらく時間がかかる。
そんな事にいちいち文句を言っていては、とてもじゃないがアジアの旅はやってられない。
走っていればいつかは着く。それくらいの気構えでちょうど良いのだ。
ところが、そんな仙人のような達観もすぐに月まで飛んで行ってしまう事になる。
何度目かの停車。
すっかり暮れた街角に少年といくぶん薄汚れた羊の群れがいる。
バスボーイがさっと降りて、車体脇のトランクを次々に開け放つ。
何をするのだろうと思っていると、突如、少年が羊の一匹を抱えて走り出した。
そうして、ばたばたと暴れる羊をトランクへと放り込んだのだ。バスボーイや他の大人達も手伝って、皆で羊を運び込む。
僕がぽかんと口を開けている横で、彼らは次から次へと、実に手際よく羊をトランクへと搬入して行った。
羊が、運び込まれて行く。
なんとも世紀末的にシュールな絵であった。
僕は思わず、隣の青年に訊く。
ねえ、ありゃ一体何やってんすか?
ああ、一つのトランクに6匹入るんだよ。全部で18匹だ。
青年が説明してくれる。
いやあの、そういう事訊いてんじゃないんすけど…。
いったいに、アジアの長距離バスは旅客と貨物の運搬を兼ねている事が多い。
運送手段を持たない商人達が、ローカルバスに大量の荷を載せて目的地まで運ぶのだ。
中国のバスには野菜が満載されていたし、ヴェトナムとラオスの国境越えバスには床一面に座席と同じ高さにまで段ボールが積んであった。
鳥籠に入れられた家禽類を見た事もある。
とはいえ、生きた羊をそのままトランクにぶち込むような超ラディカルなバスに乗り合わせたのはさすがに初めてだ。
中で糞尿が垂れ流しになったら僕の荷物にしみ込んで臭くなってしまうんじゃないだろうか。
いや、それ以前に、あんな乱暴な運び方をしたら羊は死んでしまうんじゃないだろうか。
エンジンの熱に当てられたり、窒息したりして。
だが、隣の男や他の乗客は皆一様に涼しい顔をしており、誰も驚いた風ではなかった。
この辺りの地域では、ローカルバスで羊を運ぶのは案外と普通の事なのだろうか。
バスは18匹の気の毒な羊達を載せて西進した。
夜もとっぷりと更け、月明かりとヘッドライトの灯り以外は何も見えなくなる。
僕はいつの間にか、暗い車窓に吸い込まれるように眠りに落ちた。
大きな声がして、目が覚める。
バスはいつの間にか停車している。外の方が何やら騒がしい。
車窓に目をやると、二人の男が何やら言い争っているのが見えた。
いや、言い争っているというよりは一人の男がもう一人の男に向かってなにやら言い募っているようだ。
身振り手振りを交えて盛んに何かを主張しているのは行商人風の男、それをうるさそうに聞き流しているのが軍服を着た兵士。
どうやらここに軍の検問所があるらしい。積み荷をめぐって揉めているようだ。
突然、軍人がトランクを開けた。
何の躊躇も、留保も、逡巡もなく、ものすごく唐突に。
バタンと派手な音がして、6匹の羊達が外へとなだれ出た。当然の事ながら。
べええええ、べええええええという鳴き声が夜空に響き渡る。
こんな狭い所に押し込めやがってええええ、と言っているように聞こえなくもない。
軍人は男の方へ向き直り、わずかに口ひげをゆがめてみせた。
ほれみろ、やっぱり違法な積み荷じゃないか。残りの二つも開けて調べなきゃなあ。
顔面蒼白になった行商人は、ほとんど泣きつかんばかりにして軍人に取りすがった。
ちょちょちょっと待ってくれ。
羊が入っとるのは一つだけなんだわ。もういないからさ。いやほんと。まじで。
なあ、開けんでくれよ、頼むよ!
おいちょっと…
バタン!
べえええええええ。
ひああ!
やめてくれえ。
まじでやめて。
な、頼む。
開けな…
ガチャン!
べえええええええええええええ。
軍人はあくまでクールに、行商人の必死の説得などまったく意に介さず、残り二つのトランクを次々と開けてしまった。
あっという間にそこいら中が右往左往する羊だらけになり、行商人は額を押さえて天を仰いだ。
黙示録的にシュールな絵だった。
職務を忠実に実行した軍人は、うなだれる行商人に何か一声かけてから、踵を返した。
運が悪かったな。
そうして、彼はバスにゆっくりと乗り込み、それぞれの乗客のIDのチェックに取りかかるのだった。
やがて、混乱を極めていた羊達も落ち着きを取り戻す。
行商人は肩を落としながらも羊達を先導して、砂漠の方へと歩き出した。
こんな右も左も不毛の大地に行くあてなどあるのだろうか。
羊をバスで運ぶのはイリーガルなんだ。
隣の青年がそう教えてくれる。
そりゃそうだろうよ。
月明かりも届かない闇の向こうへ18匹の羊達が遠ざかって行く。
それらは白い靄のようになり、その内に白い点になり、やがて闇の奥へと消えた。
気の毒な行商人と、もっと気の毒な羊達に、この先ささやかな幸運が訪れる事を祈りながら、僕はいつまでも夜の向こう側を眺めていた。
後年、ウズベキスタンを旅している時に、僕は同じような光景に出くわす事になる。
ただし今度は羊ではなく、2匹の黒牛だった。
牛のオーナーは(というかなんというか)何とかトランクに押し込めようとするのだが、牛の方もびびってしまって全然言う事を聞かない。
さすがに牛には馬力があり、というか牛力があり、四つ足を踏ん張って必死に抵抗する。
羊のように抱え上げて運ぶ訳にもいかない。恐怖のあまり、道路にぼたぼたと脱糞する。
あーあ、という思いで僕は、哀れな牛達が鼻輪を引っ張られ、ケツを棒っきれでしばかれながら、無理矢理トランクへぶち込まれる様を見物していた。
どこからともなくドナドナが聞こえてきそうな、シュールな絵であった。
やれやれ。
中で小便を漏らして、それが僕の荷物にしみ込んだら嫌だよなあ。
03:28:11 |
ahiruchannel |
2 comments |
25 May
旅に棲む日々 2
パキスタンを旅したのは911テロの翌年の秋の事だった。大量破壊兵器を隠し持っているから、という理由で米軍はイラク近辺に着々と軍備を展開させつつあり、きな臭い空気が遠くパキスタンにまで漂ってくるようだった。
当時の日本では(今もそうかもしれないが)マスコミの偏向放送のせいで、イスラム国は危険だというイメージが一般的だった。
パキスタンやイランへ行くと言うと、多くの人が危ないから止めろと言い、パキスタンやイランへ行ってきたと言うと、多くの人が危なくはなかったのか?と訊いた。
なるほど、そう言えばパキスタンでは最後まで外国人旅行者というものをただの一度も見かけなかった。
インドの西端、黄金寺院で有名なアムリットサルまでは確かに溢れ返っていたバックパッカー達が、パキスタン側のラホールに移動した途端に忽然と姿を消したのだ。
世界中どこにでもいるドイツ人やイスラエル人、日本人はもとより、世界一暇なオーストラリア人、なぜかバックパックに自国の国旗を縫い付けているカナダ人など、とにかくよその国では必ずと言っていいほど目にする各国の旅人が一人も見当たらない。
パキスタンは観光向けの国ではないし、観光用のインフラもまるで整ってはいないのだが、これはちょっと不気味だった。
かの国ではネットカフェを一軒も見つけられず、イランのイスファハンに辿り着くまでしばらく日本との連絡が途絶えたのだが、あと一日メールが遅れていたら家人に大使館に通報されるところだったという話や、移動中のバスで知り合った行商人グループのカシラみたいなおっさんが、お前は日本人だから歓迎するけんど、もしアメリカ人だったら後ろからズドンと打たれとるわなと言って、周りの連中がんだんだと深くうなずき、はははと頬を引きつらせながら笑ったというような話もある。
だが、パキスタンの旅は快適だったとは言い難いが、危険ではなかった。
当たり前の事だが、テロやら誘拐やら爆破やら、そんな事はどこの国であれ滅多やたらと起こるものではない。
僕が心配していたのは、ガチホモが多いと評判のラホールで、忍者屋敷みたいなゲストハウスの壁が夜中にくるりと回転して、侵入してきた髭面の大男にねじり込まれてしまいはしないかと、その一点だけだった。
僕はラホールに数泊した後、バスで国を真横に走りぬけ、イランとの国境にほど近いクエッタへと至るルートを採った。
ラホールのバスターミナルで夜行切符を買う。
切符売り場のオヤジの話では、一晩走って翌日の午前中にはクエッタに着くよという事だったが、もちろんこういう国で物事が予定通りに運ぶはずはない。
20時に発車するはずのバスは待てど暮らせどやって来ない。同じバスで西を目指すというおっさんとクエッタ行きはまだかいなまだかいなと言い続けながら、四方山話で時間を潰した。
この人はなかなか英語が達者だった。
パキスタンとインドは仲が悪いとされているけれど、本当はそうではないんだよ。
我々はもともと一つの家族なんだ。我々はインドの人々を深く愛している。でも、あっちが我々の事を嫌いなんだ。だからどうにも仕方がないよね。
ほうほう。
ただね、インドの人達が信奉しているヒンドゥー教だけど、あれは私に言わせれば宗教なんかではない。断じてない。
何と言ったかな。ほらよくあるだろう?
黒猫が前を横切ったら不吉なことが起こる、というような。
迷信?
そうそう。そういうものの集積で成り立っているんだ。とてもプリミティブだ。
ふうむ。
とかなんとか、そういうことを話しながら待つこと3時間。ようやくクエッタ行きのバスが到着。
ラホール発のはずなのに、車内はなぜか満席。
全員が煙草をもうもうとふかし、打ち捨てられた吸殻、バナナの皮や木の実の屑などが床に散乱している。
ごく控えめに表現して、拷問のような車内環境だ。
バスは走り出したと思ったらすぐに街道脇に停車し、警官が乗り込んで来た。全員のIDチェックが済むと、続いてTVの撮影に使うようなうすらでかいカメラを担いだ男が入ってきて、乗客一人一人の顔を念入りに写してゆく。
何だろう。バスの爆破テロが起こった時の為に証拠映像を残しているのだろうか?
この時点で時計の針は深夜0時近かった。
その後、バスは小一時間ほどのろのろと走ったが、またまた停車。エンジンが切られ、乗客もぞろぞろと降りてしまった。
先ほどのおっさんを見つけて声をかけると、エンジンのトラブルだと教えてくれた。運転席横の床パネルが開け放たれ、数人の男たちが口々に何かを言い合いながら、エンジンをいじっている。
車体のコンディションくらい事前にチェックしておけよな、と思いつつさらに2時間ほどが無為に流れ去る。
何度かうとうととして、空が白み始め、車窓の景色が全く違っていることに気づいた頃にバスはまた停まる。
乗客は全員降車。めいめいが水場に腰を下ろし、靴を脱いで足を洗い始めた。
水場の先には大理石が敷き詰められた広い台座のようなものがしつらえてあって、そこで男たちが頭を垂れたり、額を床に押し当てたりしている。
清冽な朝の空気の中、祈りを捧げる人々の姿が朝日に黒い影となる。
ほんの少し、彼らが羨ましかった。
結局、クエッタに着いたのは三日目の夜明け前だった。
バスは何もない平原をしばらく走って、河を越えたあたりでまた停まった。エンジンがやはり不調だったらしく、ラホールから応援を呼んでの大掛かりな修理は半日に及んだ。
行商人グループの車座に呼ばれて訊かれるままに色々と日本のことを話した。
リーダー格らしい男が、もし行きたいんならアフガニスタンに連れてってやるぞ、と冗談とも本気ともつかないようなことを言う。
でも今は情勢的にビザはもらえないでしょう?と訊ねると、ワシらについて来ればそんなもん要らんわな、うはははは、という事だった。
案外そんなものかもしれない。
この商隊のカシラはほとんど山賊みたいな風貌だったが、とても親切にしてくれた。
バスが停まる度にバナナや冷たいコーラを買ってくれたり、カレーを分けてくれたりした。
インドで人間不信に陥っていた僕は、親切にしといて最後に金を要求されたら厄介だなあなんて思っていたのだが、彼らはクエッタに着く前にさよならも言わずにどこかへ消えてしまった。
ワシには嫁が二人おってな、一人目は見合い婚だけど二人目は恋愛婚なんだわ。ほんでから子供は4人おってな。
目を細めながらそう話すカシラは幸せそうだった。
夜明け前に見知らぬ街をうろうろと歩き回っても仕方がないので、バスターミナルで日が昇るのを待つことにする。
長時間、ボロバスに揺られ続けて僕は疲弊していた。
おまけに、クエッタは高地にあるので朝晩はひどく冷える。
ぐったりとしてうな垂れていると、足元にチャイを満たしたグラスが置かれた。
見上げると、盆を抱えた頬の赤い少年が立っている。売り子なのだろう。
これを頼んだ覚えはないよ、そう告げる。
少年が顎で指し示した方には、見覚えのある二人連れがいた。
パキスタン人の一般的な民族服である白いシャルミーカワーズを着て、頭にはターバン状の布を巻き、顎鬚は白く長い。彼らも行商人の車座に加わっていたのだが、英語ができないのか、ニコニコとしているだけだったのだ。
その二人連れはにっこりと微笑んで交互に手を振り、それから大きな鞄を抱えて行ってしまった。少年も踵を返した。
僕は身をかがめてチャイグラスを取り、一口すする。
濃く、甘く、そして熱かった。
鍋に茶葉と牛乳と蜂蜜と生姜を入れて煮詰め、そして濾す。
イランから先ではチャイはいわゆるプレーンティーになるので、濃厚なミルクのチャイが飲めるのはここクエッタが最後の土地なのだ。
それは、僕が今まで飲んだ中で、掛け値なしに一番うまいチャイだった。
温かみが身体の隅々まで染み渡り、やさしく癒し、静かに心を打った。その一杯を飲んでしまった後では、僕はほとんど別人のように溌剌として、生き返ったような心地さえしていた。
大げさだが、たった一杯のチャイが世界のあり様を大きく変えることだってあるのだ。
21:12:14 |
ahiruchannel |
No comments |
05 May
旅に棲む日々 1
イスタンブールの歴史的景観区の路地裏に、日本人ばかりが泊まる宿がある。男女別になったドミトリはじめじめと暗く、便所は水が流れず、同時に二人がシャワーを浴びるとボイラーが死ぬ。
ベランダという物がないからしようがなくて地下の物置に洗濯物を干すのだが、そんな所に干しても乾く訳がなく、しまいにカビが生えたりする。
だが、最上階の共同スペースには日本語書籍と漫画本のなかなか立派なライブラリがあり、情報ノートの類も充実している。
宿代はスルタンアフメット地区では間違いなく最安値だろうし、ブルーモスクまで徒歩3分という好立地もありがたい。
宿泊者はほぼ全員が日本人パッカーなので、過酷な長旅で日本語の会話に餓えた者同士はすぐに意気投合する。
トルコ産のまずいビールを飲みながら旅とは何ぞや、人生とは何ぞやと暑苦しく語っちゃったりね。
オーナーは普段は宿には顔を出さず、長期旅行者が交代で管理人を務める。
僕が泊まった頃は女性が管理人だった。
皆彼女の事を「かんりにんさん」と呼んだので、名前は知らない。
この宿では物価の高いイスタンブールで少しでも滞在費を安くあげる為に「シェアめし」なる制度が導入されている。
材料費を参加者全員で分担し、自炊をする訳だ。費用はおおむね2〜3リラ。
街中の屋台でファストフードのドネルケバブを買っても5リラは取られる事を考えると、コストパフォーマンスは圧倒的に高い。
メニューは日替わりで、だいたいは管理人さんが献立を決め、調理も担当する。
共用冷蔵庫には本日の献立を書いた紙が貼り出され、参加したい宿泊者がそこへ名前を書き込み、代金を払う。
参加人数が多ければ当然飯は豪華になるし、逆に少なければつましいものとなる。
さて、初めてこの宿を訪れた日の献立は「カルボナーラ」であった。
僕はカルボナーラについては、というか、パスタ全般に関して一家言ある人間である。
レストランなんかで料金以下の半端な皿を出されると、俺が作った方がうまいよと呟くようなタイプの人間である。
冷蔵庫にはオリーブとアンチョビとケッパーとパルミジャーノを常時ストックし、麺は多少高くてもバリーラを選び、茹で時間を計るキッチンタイマーは秒単位でセットしてあるという人間である。
出されたパスタになーんも考えんとタバスコをぶっかけたり、テレビを見ながら麺を茹でてアルデンテのタイミングを見誤るような輩は地獄に落ちればいいと考える、そういう人間である。
その宿に荷を降ろした時には丸4ヶ月間パスタを口にしていないというコールドターキー状態の最中であり、ここで他人が作ったまずいパスタなんか喰わされて発狂したくないという強い思いが沸き上がり、差し出がましくもカルボナーラはわたくしめがお作りいたしましょうと管理人さんに申し出たのは極めて自然な流れであった事はご理解いただけると思う。
管理人さんは大喜び。
よかったあ、実はカルボナーラってどうやって作るかよく知らないんですよお〜。(なぜ献立表に書いたのだ?)
じゃあ買い物は私がしてきますので。何でも言って下さいね。
僕は絶句しかけたが、気を取り直して笑顔を作る。管理人さんは基本的に善の人なのだ。
任せてください。カルボナーラは得意中の得意ですから。
ご存知ない方の為に簡単に説明するが、カルボナーラとはベーコンと粉末状のハードチーズで作るソースを太めの麺に絡めていただくシンプルな一品である。
美味さの決め手はベーコンの脂と濃厚な味わいのパルミジャーノレッジャーノ。
これに卵黄を加え、クリームは使わないのが正当派ローマ風だ。仕上げに黒胡椒をぱらり。
パルメザンチーズと称して円筒形の容器に入っている粉チーズがあるが、どのレシピ本にもあれだけは絶対に使うなと書いてある。
必ずパルミジャーノレッジャーノか、ペコリーノロマーノを使いましょう〜云々。ベーコンもできればイタリア産のパンチェッタが好ましい。
僕は別に権威主義者ではないが、カルボナーラに関してはこれは全くの事実だ。
上等のベーコンとパルミジャーノがないと、この料理は成立しない。
何を買いますかあ?とメモの準備をする管理人さんに、僕はご託宣をたれる預言者のようにおごそかに告げる。
「まず、ベーコンのブロックを…」
「あ、それはありません。トルコにベーコンはないです」
乾いた一陣の風が僕と管理人さんの間を吹き抜けた。
イスラムの国ですからねえ〜、と彼女はあくまでにこやかに言う。
「代わりに鶏肉でもいいですかあ?」この人は善の人なのだ。僕はしばし言葉を失う。
カルボナーラはベーコンがないと成立しない。僕のプロットはいきなり破綻をきたした。
「えと、それではパルミジャーノレッジャーノというハードタイプのチーズ…」
「それもきっとないと思いますよお。代わりに白チーズでいいですかあ?」
「あの、えと、じゃあ、フェットチーネと申しまして、平麺なんですけど…」
「ロングパスタは高いんですよお。一人2リラだと予算オーバーだからマカロニでもいいですかあ?」
「………」
僕があほうのように口を開けて完全に沈黙してしまっても、管理人さんは微笑みを絶やさない。
繰り返すが、この人は善の人なのだ。
悪気は、まったく、ない。
結局、要求した食材で用意された物は卵とオリーブオイルだけだった。
僕は力なく鶏肉に大蒜の香りをつけてソテーし、それにすり下ろした白チーズと卵黄を混ぜ、茹でたマカロニにかけた。
自分の作ったものが一体何なのか全くわからなかったが、それは「カルボナーラ」として宿泊者に配られたのだった。
信じ難い事に、みな口々にうまいうまいと言ってそれを平らげたのだ。それは余計に僕を脱力させた。
翌日、献立表には「ペペロンチーノ」と書かれてあった。
僕は絶望的な気分でその文字を眺め、しばし天を仰いだ。
気配を感じて振り返ると、管理人さんが目を輝かせて僕を見つめているのであった。
02:37:04 |
ahiruchannel |
4 comments |
23 October
after hours 3
パンツいっちょになって姿見の前に立ってみた。不自然な格好に首をひねって、己が肉体を仔細に点検する。後ろの方では姐さんが口をぽかんと開けている。
だが、決してギリシア神話に出てくる誰かのような自己愛をもってそういった行為に及んでいる訳ではないのだ。
両脚、両腕、シャツの襟ぐりがあたる鎖骨のあたり、パンツのゴムひもがあたる腰まわり。
それら全ての部位に無数の赤い斑点が浮かび上がっている。
とてつもなく痒い。我慢できずに掻きむしってしまう。
何か深刻な病気に罹患したのだろうかという暗い予感が一瞬頭をよぎる。
そう、ウィルス性の致死的な病を思わせる不吉な赤斑は日に日に増えているのだった。
ブダペストでの安穏とした日々に別れを告げ、アドリア海を目指したのがちょうど一週間前だ。
出発は早朝4時45分だった。
週に二便しかない格安バスはネプリゲットバスターミナル近くの路肩から発車する。
鉄道でクロアチアやスロヴェニアを目指すとなると、すぐに100ユーロ200ユーロという話になってしまうのだが、このバス会社は片道たったの15ユーロ弱という信じられない安さであった。
安さの秘密は、ターミナル敷地外の一般道路を勝手に使って離発着している事にあるのだろうか。チケット購入もエージェントを通さずネットでのクレジット決済のみ。
極めてシンプル、余計な経費がかからない分、乗車料も安いのだろう。
こういうシステムのバス会社がもっと増えればいいのに、と思う。
ヨーロッパにおいてバックパッカーの頭を最も痛めるのが、法外とも思える交通費の高さなのだ。
空はまだ白みきらず、夜気が冷たく身体をつつむ。
長期滞在者の主様と、宿のオーナーのヨシさんと、長期旅行者だとは到底思えない程身ぎれいなユウコ女史がそれぞれ見送ってくれた。
沈没生活のお陰ですっかり夜型人間になってしまった僕は、朝起きる自信がないので肚をくくって徹夜を決め込んでいたのだ。
主様も、僕と同じく普段から夜更かし組だったが、この日、彼は真夜中を過ぎてもなぜかベッドへ行こうとしなかった。
出発の時になって、僕らを見送る為にわざわざ起きていてくれたのだと気づく。
ユウコちゃんは名古屋でネイルサロンを経営する美意識の高い女性だ。
夜明け前に眠たい眼をこすりながら起きてきた割には、ばっちりメイクがなされていた。さすがに美のプロである。
ほとんど僥倖とも言える偶然の末に相見え、ひととき言葉を交わし、そして、皆がまた別々の方向へと旅立ってゆく。
またどこかで会いましょうと言い交わし、宿を後にした。
またどこかで…。
今回のアドリア海南下の旅には道連れがいる。
美大を卒業し、バーの店長や板前などの職を経て、ヨーロッパの街並を絵にしながら旅をしているという異色のパッカー、ナオキくん。
馬鹿重い画材を背負ってブダペストへやって来た酒好きの彼と、同じく阿呆みてえに重いギターをぶらさげた飲み助の僕とはすぐに意気投合した。
彼はクロアチアへ、僕はスロヴェニアへと行く予定でこの日の切符を買ってあったのだ。
方角は同じ。彼が先に下車するはずだった。
ところが、どうした訳かこの日アドリア海方面へ向かう便はクロアチアの首都ザグレブを経由しないのだという。
今週はクロアチア通過の為のパーミッションを取っていません。よってザグレブでの途中下車はできません。
アテンダントはそう説明する。
なんじゃいそりゃ?
先週までできていたことがなぜ今週になってできなくなるのか?
しかし、そんな些細なことにいちいち文句を言っていてはとてもじゃないがパッカーなんかやってられない。
旅とは、いわばおびただしいトラブルの集積でもあるのだ。
ここでナオキくんの予定に若干の狂いが生じ、僕と共にスロヴェニアへ向かうことを余儀なくされる。旅は道連れだ。
首都リブリャーナは小さな小さな街だった。
小高い丘の上の王宮が街を見下ろし、川が流れ、教会がそこかしこに点在するという典型的なヨーロッパの都市風景。
だが、その規模があまりにこぢんまりとしているので、プラハやブダペストのミニチュアのように感じてしまう。
こんな事を言うと観光局あたりに怒られそうだけど、特に感興をそそるものはない。
あてもなくうろうろと歩き回り、駅前の野外パブでビールを飲んだだけ。チェコ以来の冷えた生ビールだけはなかなかいけた。
翌日は郊外のシュコツィアン鍾乳洞なるものを見に遠足を実施。
この洞窟はヨーロッパ随一の規模なのだとか。
僕は鍾乳洞なんぞには特に興味もなかったのだが、行ってみるとそれはそれでなかなか良いものだった。地下の目も眩むばかりの大渓谷もさすがの迫力だった。
面白かったのは、鍾乳窟内ツアーにおけるガイド言語がイタリア語と英語の選択制になっていることだった。
そう、スロヴェニアは旧ユーゴとはいえ、アドリア海をはさんでイタリアと向き合う国なのだ。
実際、リブリュアーナの街にはイタリアンレストランが軒を連ねていた。
パスタの味はまあまあ、可もなく不可もなくといったところ。
値段はしっかりユーロプライスだった。
スロヴェニア滞在はわずかに二日。翌々日の朝の列車でクロアチアへ移動。
首都ザグレブは旧共産圏特有の暗灰色に塗り込められていた。
宿に荷を降ろすのももどかしく、すぐに近所の市場へと向かう。
生ハム200グラムに巨大なチーズの塊、それにビールを半ダース、祝杯と称して真っ昼間からささやかな宴を催した。
何がめでたいのかはよくわからないが、つまみどれもはっとするほど美味しかった。
さすがにここはヨーロッパなのだ。
量り売りのハムやチーズにさえ連綿と受け継がれる伝統を感じる。味が、本物だ。
僕はそれを「ヨーロッパの底力」と呼んでいる。
この日より以降、市場でハムとチーズを買い求めることが我らの日課となる。
ブダペストでの堕落の日々が嘘のように、僕は高速で移動していた。
全ては活動的なナオキくんのお陰である。
純粋な好奇心を失わずに、前へ前へと進んで行く彼に引っ張ってもらう形で、僕の旅も加速してゆく。
翌朝にはもうザグレブを出発、プリトヴィッツェ国立公園を経由して、その日の内にアドリア海沿岸の街スプリットへと抜ける。
この日、プリトヴィッツェでは市民マラソンが開催されており、周辺の道路は封鎖。
バスは途中で立ち往生、辿り着くのに結構な時間を要した。
マラソン大会の事は、僕よりも少し先に同じルートを行く姐さんから聞いていた。
(ブダペストで一緒になった、30代女性パッカー。詳しくは前回の項を参照)
とにかくそんな事情なので、本当に走るのかと僕はバス会社のカウンターで訊いてみたのだが、マラソン大会?何それ?というような、なんとも心もとない反応だった。
案の定、途中で足止めを喰らい、封鎖が解けるまで何時間も街道で待つことになる。この辺がいかにも旧社会主義的ないい加減さだ。
マラソンとの兼ね合いを考えてタイムテーブルを臨時に調整するとか、いろいろやりようはあるだろうに。
何の為にあんなに早起きしたと思ってるんだ。
悪いことは重なるもので、車内アナウンスがなかったせいなのか、我々は目的地で降り損ねてしまったのだ。
異変に気づいて僕がバスを止めたのは既に目的地を何キロも過ぎた地点だった。歩いて戻れと言い捨てて走り去るクソッタレバス。
親切なクロアチア人がヒッチハイクに応じてくれたから良かったようなものの、炎天下にクソ重いギターと画材を抱えて歩く我々は遠からず干上がってしまっていただろう。
その腹いせにという訳でもないが、プリトヴィッツェ湖沼公園には入場料を支払わずに不法侵入した。
公園の内も外もマラソン関係者でごった返していて、旅行者との見分けなどつくはずもなかった。
良きことがあり、悪しきことがある。
ここで九日ぶりに姐さんに再会、我々のパーティーは三人になった。
完全に陽が沈みきってから、スプリットへ到着。姐さんは前もって予約をしてあった日本人宿へ、我々は宿代をケチって民泊することに。
この判断ミスが後の恐ろしい赤斑の元凶となるのだが、その時はもちろん知る由もない。
スプリットはなかなかに風情のある街だった。
アドリア海の蒼に赤い瓦屋根が映える。どこを切っても絵はがきのような情景だ。
港に繋留された巨大客船の白い船体が陽光を眩しく照り返し、ビーチでは逆光を受けた海水浴客の黒いシルエットが波間に踊った。
港町はいい。よくよく考えてみれば、僕が好きなのは全てが港町だ。
イスタンブール、バルセロナ、香港、エッサウィラ、フリマントル、そして神戸。
スプリットには都合三泊し、近郊のシベニクという町へも足を伸ばした。
この頃から、手の甲に例の赤い斑点が出始めたのだ。それも一つや二つではない。
タチの悪い蚊に喰われてしまったのだろうか。痒くって仕方がない。
それで、観光に訪れたはずのシベニクの町で最初にした事といえば薬局探しであった。
化粧品屋を兼ねた店なので、店内には女性客しかいない。クロアチア語はさっぱりわからないから、あれでもないこれでもないと、品定めに時間がかかる。
おまけに、虫除け薬品の棚は生理用品コーナーのすぐ隣にあったりして、意味もなく汗をかいてしまう。別に怪しい者ではないのですぅ。
苦心の末、ペンシル型の容器に入った塗り薬と思しきものを選んだ。
例によって例のごとく、店員のお姉さんには英語が通じない。患部を見せて、この薬で大丈夫か?と身振りで訊ねる。
この薬はたいして効かなかった。
いや、効いたのかもしれないが、新しい斑点が次から次へと生まれて来るので、結局かゆみは断続的に続くことになる。
斑点は今や両腕だけでなく、脚にも現れ始めていた。
スプリットを後にし、フェリーでアドリア海を南下する。
目指すは世界遺産の街、ドブロブニク。別にバスで行ったって良かったのだが、我々全員が倍も時間のかかる船旅を選んだ。
何しろここは名にしおう紺碧のアドリア海、船に乗らないという手はない。
船酔いする前に酒に酔ってしまおうと目論んで、ワインと生ハム、チーズを持ち込んだ。
重油臭い二等客室とはいえ、船上で飲む酒は格別だ。塩気の強いハムもワインにはよく合う。
その昔、イタリアの踵からギリシアのペロポネソス半島へ船で渡った時も、甲板で一人酒盛りをやったものである。
そんな具合に、酒を飲んだり、映画を観たり、適当にその辺に横になって昼寝などしている内にドブロブニクに到着。
客引きに言われるままに、港からほど近い民宿へチェックイン。三人で部屋をシェアする事になった。
そして、僕は荷物を置くなり、やおら着ているものを脱ぎ散らし、鏡の前に立ったのだった。
ここで、ようやく冒頭の場面へと至る。
自分の身体ながら、あちこちに赤い斑点をこしらえた様はかなり異様だった。
そして、間歇的に襲い来る頭がおかしくりそうな堪え難い痒み。
これが現れたのはつい昨日のことなのに、今やそれは黙示録的に増えつつあった。異常なスピードだ。
がん細胞があっという間に全身に転移し、骨や脳髄までをも侵す様を僕は思い浮かべる。
スプリットの民宿のベッドに虫が潜んでいたのだ。それ以外に原因は考えられない。
そしてその虫は僕のTシャツやジーンズに乗り移った。おそらくは。
この種の吸血性の寄生昆虫で、人間の生活圏内にいるものでは、ノミ、シラミ、ダニなどが考えられる。
その昔、猫を飼い始めた時分には、ノミに随分悩まされた。
こいつらは人の服に潜むのである。
なんだか脚がばかに痒いなと思って、ズボンの裾をまくり上げてみると、ピョーンと飛んで出たこともある。
その幼虫が床を這いずる様も、見ていて決して心和む種類の光景ではない。
僕はまだ小さかった猫を、何度も何度も風呂へぶち込み、ノミ取りシャンプーで泡立てた。
そのたびに、こいつは情けない声をあげてよろよろと逃げ惑ったが、委細構わず湯をぶっかけ、タオルでごしごしと拭いて、それからヘアドライヤーで乾かした。
ノミ取り用のブラシで梳り、石鹸水を張った洗面器に捕えた虫をつけて抹殺した。
月に一度は害虫駆除の煙を炊き、部屋を念入りに掃除した。それでもノミは決して絶滅しなかった。たまらんよ、これは。
結局、動物病院で完全にノミを駆除できる薬が処方されているのを知ったのは、そんな不毛な戦いを一年近くも続けた後だったのだ。
だが、スプリットの民宿には猫も犬もあひるもいなかった。
この刺し痕はノミではない。
トコジラミ、別名南京虫は日本ではもう目にすることもないが、海外の不衛生な宿屋には今でもしばしば出現する。
南京とは外来のという意味の昔風の接頭語だ。南京豆、南京錠、南京玉すだれなど。維新頃、海外からの積み荷にくっついていた虫が、日本に広まったとされる。
当時は神戸港近くに大量に生息していたのだとか。たまらんなあ。
だが、こいつは成虫になると体長8mmにもなるので、当然目視が可能である。
僕はシャツをひっくり返して、襟や袖口の縫い目の所を仔細に点検したが、それらしい虫はいない。
だとすると、ダニか。
ダニの種類は世界中で実に二万種を数えるらしい。たまらんなあ。
もし昆虫類が今の何倍かの大きさを持っていたら、世界は全く違った様相を呈していたであろう。
子犬ほどもある二万もの色とりどりのバライティ豊かなダニどもが、そこいら中をうろうろとする様を想像していただきたい。
噛み付かれて血を吸われたりしてね。思わず貧血になりそうである。
問題は、視認できない怪しい虫が僕の服に潜んでいるらしい事である。
痒い痒いとのたうち回る。見かねた姐さんが「ムヒ」を貸してくれる。
前述したが、このお方は大変しっかりと準備をして旅をしておられるのである。
虫に刺される可能性なんか全く考慮に入れていなかった誰かとは大違いだ。
だいたいにおいて、僕は日焼け止めや虫除けや下痢止めといった基本的なものを何一つ持っていない。風邪薬さえもない。
あるのは持病の偏頭痛の薬くらいのもので、後は譜面台とかスピーカーとか、そういう重くてかさばるような、愚にもつかないものばかりである。
痒みに耐えながらも、翌日からドブロブニクを観光して回った。
街が見下ろせる丘に何時間もかけて登り詰め、死にそうになった。
何しろ石がごろごろと転がる斜面をサンダル履きで歩んだのだ。しかし山頂からの景色は掛け値なしに素晴らしかった。
教会前の広場で日光浴をする猫たちと遊んだ。
魚介を喰わせる老舗レストランでは白ワインで生牡蠣をたっぷり堪能した。ワカサギフライもいけた。
もっとも、かなりの分量を足下の猫に食べられてしまったが。ここは東欧でも指折りの猫町なのだ。
船で近隣の島へも渡ってみた。
ここにはなぜか野性の孔雀がたくさんいて、メイオーメイオーとやかましく騒ぎ立てていた。
ヌーディストビーチにも足を伸ばす。
ビーチというか、波打ち寄せる岩礁なのだが、とにかく入り口には着衣での入場禁止と立て札が立っている。
ナオキ君は迷うことなくパンツを脱ぎ捨て、股間のあたりをぶらぶらさせながら勇ましく先陣を切った。
僕は冷やかし半分でついて行っただけなのだが、彼の益荒男ぶりにいたく感じ入り、やはりパンツを放り投げてぶらぶらと後に続いたのだった。
残念ながら、若い女性の姿はどこにもなかったことを念の為申し添えておく。
しかし、これはなかなかに気持ちのいいものであった。素っ裸で潮風に吹かれるなんて経験はなかなかできるものじゃない。
取り残された姐さんがビーチの入り口でむくれていた。ま、日本人女子はなかなか入りにくいだろうな。
こうしてドブロブニクでの三日は瞬く間に過ぎた。
衣類に住み着いた虫たちは、その間も僕の血を吸い続け、赤く不吉な痕を次々と作った。
姐さんに借りたムヒは目に見えて減りつつあった。塗っても塗っても間に合わないのだ。
どうしても掻きむしってしまうので、肌はボロボロになる。
痒い痒いとうめきながらもクロアチアに別れを告げ、さらに南下。バスでモンテネグロへと向かう。
ドライバーもアテンダントも、とてもカタギとは思えないような目つきの悪い連中だった。
旅行客が荷物を固めて置いてあるあたりにバスの鼻先を乱暴に突っ込み、それらを蹴散らした。
客の誰かが注意すると、文句あんのか?とギャングさながらのいかついガンたれ。先ほどまでなごやかに談笑していた乗客たちの顔がさっと引きつった。
マフィアがユーゴ解体で落ちぶれて、バス会社に就職したのだろうか。我々はそのバス会社をヤクザバスと命名した。
二時間半かけて、四方を山に囲まれた入り江の町、コトルに到着。
モンテネグロはイタリア語で黒い山を意味するが、その名の通り、山肌は黒々としている。
だが風景に目を向けている余裕はない。
民宿に着くなり、僕は着ているものを脱いで、湯をわかしにかかった。
かの深夜特急には、インドのアシュラムで子供達の衣類についたシラミを退治する場面がある。ドラム缶に湯をわかし、そこへ服を叩き込むのだ。
僕はスプリットでもドブロブニクでもちゃんと衣類を洗ったが、赤斑は増える一方だ。洗濯したくらいでは虫は死なないのだ。
煮えたぎる湯の中にぶち込んで息の根を止めるしかない。
だが、電気コンロの栓をひねった途端に、あっけなく家中の電気が落ちた。
ううむ、この貧弱なインフラ。旧共産圏よのう。
電気の回復を待って、煮沸開始。
ここで、姐さんのお役立ちグッズが次々と登場した。まずは電熱コイル。
水を満たしたコーヒーカップにこいつを突っ込むと、すぐに沸騰するというあれだ。
弱々しい電気コンロだけではさっぱり湯がわかないので、電熱コイルを鍋のふちに洗濯バサミで固定する。
それから携帯用の箸。衣類を煮るにはまさに理想的なアイテムだ。
シャツやらパンツやらを一枚一枚、まるでしゃぶしゃぶのように、姐さんが煮え立つ鍋の中を泳がせる。
その間、彼女は死ね死ね、ムシ死ねと念を送り続けた。
そして、ホカホカと湯気を立てる衣類を僕が風呂場へ運び、タライに水とありったけの洗剤を入れて死ね死ねとかき回す。死ね死ね。
これで、日光にあてて乾かせば完璧なのだが外はあいにくの雨。仕方なく軒下に干して、ようやく一息ついた。
姐さんがTシャツとズボンを貸してくれる。本当に気の利く人なのである。
我々は最大限の敬意を込め、彼女にドラミちゃんというあだ名をおつけして差し上げたのであった。
依然天気は悪かったが、三人で街まで出た。
歩いている内にまた堪え難い痒みが襲ってくる。今朝新たに噛まれたと思しき場所が腫れ上がって、掻けば掻く程ますます痒くなる。
何度も何度も掻いていると、刺し痕がない部分まで痒いような気になり、果ては内臓や骨、脳までもが痒みを訴えだす。
段々と凶暴な気分になってくる。
無性に腹立たしい気分になってくる。
世の中の全てのものを呪いたいような気分になってくる。
今からスプリットに引き返して、あの民宿のあのベッドを焼き払ってくれようか。
いや、いっそのこと両手と両脚と首を切り落としたらすっきりするんじゃないだろうか。
古今東西、痒みに耐えかねて自死を選んだ人はいたのだろうか。今よりもっと不衛生だった時代には、全身を南京虫にやられて発狂した人がいたかもしれない。
駄目だ、ギブアップ。
僕のせいでさっきから二人に迷惑をかけっぱなしなのは申し訳なかったが、目についた薬局へ飛び込んだ。
例によって患部を見せ、とにかく痒くて死にそうです、切ないです、辛いです、と訴える。
薬剤師さんはいたってクールだった。ちらとも同情の眼差しを向けるような事はなかった。
なるほど、痒いというのは本当に個別的な体験なのだな。
痛みはある程度共有できるかもしれないが、痒みを分かち合うなんて話は聞いたことがない。
僕は重度の花粉症患者でもあるのだが、花粉症の症状を他人に説明する時にも、人はおおむね同じような反応を示す。
いやもう何しろ痒くてね、眼球を取り出して水洗いしたいです。僕のそんな訴えは、決して大げさではない。
それを聞いた人はすべからく、へえ〜そりゃ辛そうですねえ、と一応慰めの言葉らしきものをかけてくれる。
だが、目は完全に笑っている。
クソッタレが。お前の目ん玉取り出したろか、という気分にもなる。
処方されたのは、チューブに入った塗り薬だった。いかにも医療用という味も素っ気もない外装。
これ何の薬ですか?と訊くと、一言、アンチヒスタミニックという言葉が返ってきた。値段は2ユーロ。
ドラミちゃんは蚊取り線香を購入していた。
賢明な判断だ。この上蚊にまでボコボコにやられたら目も当てられない。
教会を見学してくるという二人を見送るやいなや、ズボンの裾をまくり上げ、薬をせっせと擦り込んだ。
本当はシャツもパンツも全部脱いでしまいたかったのだが、さすがにそれをやると逮捕されてしまう。新聞にも載ってしまう。
一匹の猫が遠くから、こいつは何をやってるのかしらん?という目でじっと見つめている。
君にも塗ったろか?
これは効いた。劇的に効いた。痒みが嘘のようにさっと引いた。
シベニクで買った痒み止めも、ドラミ姐さんが貸してくれた正統的日本のムヒも、まったく比較にならない程のこの効果。
後から冷静になってみれば、これは「劇薬」の類いだったと推測できる。だが、その時は痒さで気が変になりそうだったのでそこまで考えが回らなかった。
当然、後からその報いを受けることになる。
翌朝も篠つく雨。
これでは大量の洗濯物が乾かない。
今更ながらに、自分の間の悪さを呪いたくなる。
僕は自他ともに認める最凶の雨男なのだ。
さっきまで晴れていたのに、玄関を出た途端、洗濯物が仕上がった途端、雨がパラパラと降り出す。
あるいは、濡れて帰って来て、後ろ手に扉を閉めた途端に晴れ間がのぞく。
仕方なしに生乾きの洗濯物をパッキングし、三人でまた街へ出た。
この日は土曜日、中心地には朝市が立っていた。
肉、鮮魚、青果、ドライフルーツ、チーズ、ハム、油、などの生活必需品。
規模は小さかったが、市場というものは常に楽しい。
どのガイドブックでも取り上げる観光名所よりも、こうした地元民の為の市場こそがその国の世情を最も反映しておるのである、とかそんな聞いた風のスノッブな理由ではなしに、純粋に楽しい。
特にチーズの売り場に風情があった。おらが村でじいちゃんとばあちゃんが作りましたというような、素朴な手作りチーズが所狭しと並ぶ。
見るからに酸っぱそうなフレッシュチーズ。一冬熟成させたというような茶色味がかった丸チーズ。試しに一つ買って帰りたかったが、今日中に隣国へ移動するので我慢。
街の広場には年配の日本人団体旅行客。アドリア海沿岸周遊の旅は、目新しい観光スポットとして人気があるのだろうか。スロヴェニアでも、クロアチアでも団体客を数多く見かけた。
彼らは一様に「耳太郎」という小道具を携帯していた。
みんな「みみちゃん」っていう愛称で呼んでるのよ、と一人の中年女性が教えてくれた。
一見小型ラジオ風の筐体からイヤホンが各人の耳に伸びている。これで添乗員の声を無線キャッチするのだそうだ。
現地ガイドの説明を添乗員が通訳し、それをさらにみみちゃんが旅行客の耳へ直接送り届ける、という訳だ。
いかにも日本的な気配りというか、余計なサービスというか、なんというか。
ちなみにコミュニケーションは一方通行で、顧客の声を添乗員に返す事はできない。
トランシーバー機能を持たせるなど雑作もない事だろうが、それをやると口うるさいじじばば共が勝手な事を言いまくって、添乗員さんはすぐにストレスで鬱病になってしまうだろうな、と容易に想像できる。
この日、団体客を引率していたのは若く奇麗な女性だった。
ひとしきり城壁内の観光を終えて、これから解散しての小休止に入ろうとしているところのようだった。
我々はその様子を見るともなしに遠巻きに眺めていたのだが、突如ドラミ女史が、あのおねーさんナンパしてお茶しようよ、と言い出した。
若くて可愛いのに、老人の相手ばっかりできっと同世代と話したがってるよ、と。
僕とナオキ君は顔を見合わせたが、ドラミさんは委細構わず歩いて行ってしまった。突然何を言い出すんだあの人は?
見るからに社会不適合者のバックパッカーと、大手(かどうかは知らないが)旅行社のエリート添乗員が話なんかしたがるものだろうか。
だいたい、僕は見知らぬ人に声をかけるという行為がものすごく苦手だ。ナンパなんか未だかつて一度もした事がないし、道を訊くのだって結構な勇気が要る。
だが、ドラミさんは添乗員のおねーさんをいとも簡単に連れて来てしまった。手品でも見ているみたいだった。
僕はその社交性というか、人当たりの良さというか、コミュニケーション能力に内心舌を巻く。絶対に真似できない。
きちんと化粧をし、まともな衣装に身を包んだ、背筋の正しい美人だった。こういう「普通の」美しい日本女性を目にするのは実に久しぶりだった。
絶対にお客さんに見つからない、お店の一番奥でなら、おつきあいさせて頂きます、と彼女は言った。
僕とナオキ君は顔がにやけそうになるのをこらえつつ、薄暗いカフェの奥へ移動した。それぞれにカプチーノやらビールやらを注文する。
添乗員さんは、ようやく肩の力を抜いて、タバコを一本口にくわえた。
お客さんの前では絶対に吸えないんです、と打ち明けるように彼女は言う。
年配の方が多いから、若い女性の喫煙を快く思わないし、中には怒り出す方もおられて…。
なるほどなあ。若くて美しく有能な添乗員である為には、いろいろと気苦労も多いのだ。
歳くったお客を引率するのは、やはり想像を絶する激務であるらしい。
何から何まで気を配って、面倒を見て、食事の際もつきっきりで、自分はお客の休憩時間にスケージュールを確認しながら飯をかき込む。
誰よりも早く起床し、誰よりも遅く就寝する。集合場所には定刻の15分前には行く。それでも、生真面目な日本人達はもう集合している。
ほとんどの場合引率は一人だから、歳の離れたお客とはろくに話も合わないだろう。
随分孤独な仕事だろうな、と思う。海外へ行けるという余録はあるにしても、こうも四六時中気を張っていては身が持たないだろう。
我々は、ほんの一時でも彼女を楽しませねばという使命感に駆られたのか、添乗員には想像もできないような旅の馬鹿話を次々と披露して、場を盛り上げた。
この人なんかね、クロアチアで虫もらっちゃって、せっかくモンテネグロに来たっていうのに、最初にやった事が衣類の煮沸ですよお、とドラミさんが言う。
そうそう、ほんと何やってんでしょうねえ、と僕も調子を合わせる。添乗員さんは可笑しそうに笑う。
ひとしきり笑った後、ありがとうございます、本当に楽しかったです、と言って彼女は仕事に戻った。
自分の分の勘定を素早くテーブルに置こうとした彼女を僕ら全員で押しとどめた。
大変な仕事だろうが、どうか頑張って頂きたいと思う。
その日の午後のヤクザバスで一度ドブロブニクまで引き返し、乗り換えをしてボスニアヘルツェゴビナへと向かった。長時間の移動だ。
途中の休憩所の汚いトイレは1ユーロだった。ぼったくりもここに極まれりというところだ。
切符を切りに来た車掌には、モスタルで降りるからと告げておいた。
にも関わらず、またしても我々は降り損なってしまった。ボスニアのバスも負けず劣らずヤクザだったのだ。
到着予定時刻を過ぎても、一向にそれらしい場所が見えてこず、いつまでも薄暗い街道を走り続けるバス。
僕がどうにもおかしいと思ってバスを停めた時には、すでにモスタルから致命的に離れてしまっていた。
もう夜更けと言ってもいい時間帯だ。降ろされた駅の周辺には街灯ひとつない。
同乗していた地元の女子大生達が、我々の代わりにクレームをつけてくれた。
どうも途中で車掌が交代したらしく、前任者は不案内な異国人が乗車している事を引き継がなかったのだ。
もう、この辺が本当に旧共産圏の悪しき伝統だよなあ。サービスという概念が社会にまったく浸透していない。
バスなんか、とにかく走りゃそれで文句ねえだろう?後はおめえらで勝手に乗り降りしろや、という経営姿勢がありありなのだ。
明日新聞に投書してあげるから、と息巻く女子大生達に僕らは礼を言う。
とは言っても、目的地に気づかなかった我々にも若干の責任はあるだろう。仕方ないので、モスタルまでは白タクを使った。
我々三人と、同じく降り損ねたアイリッシュの女の子の二人で、しめて70ユーロ。一人頭14ユーロの計算である。
一日分の宿代が奇麗に飛んだ。痛い。
走れども走れども、一向にモスタルに着かない。
二時間が過ぎ、三時間が過ぎ、一体我々はどれくらい行き過ぎたのだろう、と訝しみ始めた頃、ようやく街灯りが見えて来た。
大きな街だった。僕はドブロブニクから一睡もせずに、景色を見ていたので断言できるが、バスはこんな場所を通っていない。駅前のターミナルにも全く見覚えがない。これを見過ごすバカはいない。
あのヤクザバスはモスタル経由とうたっておきながら、当の街をかすりもせず、全然別の道を走っていたのだ。
はっきり言って滅茶苦茶である。我々に瑕疵は全くなかったのだ。クソッタレヤクザバスめが。
これが、旧ユーゴという場所だ。これから個人で旅行に行かれる方は心して頂きたいと思う。
そんなこんなで、日付けもとうに変わってから民宿にチェックインできた。
僕の身体にはコトルでの煮沸以来、新しい斑点はできていない。
代わりに、薬を塗った個所が大きく腫れ上がってきていた。痒いと思ってうっかり触ってしまうとかなりの痛みが走った。
前日の薬に問題があるのは明白だった。あるいは、ステロイドなどの危険な成分が入っていたのかもしれない。
散々である。
しかも、僕と同じ宿の同じ部屋に泊まったのに、ナオキ君のベッドには虫がいなかったのか、彼はまるで平気そうな顔をしているのだ。
神はかくも我らを不平等に創り給いけり。
翌日は首都であるサライェヴォに移動した。
日本人男性を専門に狙って喰ってしまうという恐ろしい民宿の女将に追いかけられたり。
有名なオーストリア皇太子暗殺事件の現場を見学したり。観光客が大勢いたのでそうと分かっただけで、何の変哲もない普通の橋だった。
先の戦争中、ここを歩く者は老いも若きも男も女も関係なくセルビア兵に狙撃されたというスナイパー通りを歩いたり。
教会とトルコ系のモスクが一つの街中に混在しているのがシュールな絵だったり。
宗教や民族が原因の対立は今もって根が深いと聞く。
山肌に妙に墓場の数が多いのも気になった。財政難で再建の目処が立たないまま放置され、観光遺跡と化した公共施設の数々。
安易な表現だが、戦争の爪痕という言葉がしっくりくる情景だった。
そして、首都にもやはり一泊しただけで、翌日、僕らはほとんど一日がかりでブダペストへと帰ったのだった。
列車の中ではまた酒盛りをやった。ハムにチーズ。そして馬鹿話。
アドリア海南下の旅もこれにて終了だ。
正確には、アンダンテホステルへ帰って来たのだ。
我々はみな、この宿で出会い、別れていった。
二人はいい旅の連れだった。
僕はいついかなる場合も一人で旅をする、孤独を好むタイプのパッカーだが、たまにはこうやって道連れができるのも悪くない。
いや、もっと積極的に言おう。楽しかったのだ。
いろいろと苦労もしたが、楽しかった。
この後、僕はすぐに友の待つバルセロナへと飛び、モロッコを周り、たった一週間の一時帰国を経て、オーストラリアへと渡る。
姐さんは、アンダンテホステルの臨時スタッフとなり本格的に沈没。今もまだ旅を続けている。
ナオキ君からは、先日、ようやく日本に帰ったとメールが届いた。まじ一緒に飲みたいっす!と。
繰り返しになるが、ほとんど僥倖に近いのだ。
旅というその一点でのみ、我々はつながり、切れ、時にまたつながる。
また会えるかもしれない。会えないかもしれない。
あるいは、もうこういう旅は二度とできないかもしれない。
ただ、僕たちが共有したある種の時間の断片、ある種の記憶の断片は、この先、我々の寒々しい人生をちょっぴりだけ暖めてくれるのではないだろうか。
そんな気がする。
身体の腫れは数日でひき、その後虫に喰われる事はもうなかった。
でも、一時帰国した折り、僕が真っ先に買い求めたのは、虫さされの薬だった。
01:50:54 |
ahiruchannel |
No comments |